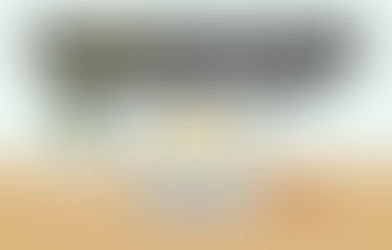「生産性低下」の真相とは?テレワークに見る課題と解決策
- FuvaBrain
- 8月7日
- 読了時間: 11分
更新日:2025年8月7日

テレワークの普及により、働き方の柔軟性が増す一方で「生産性の低下」を懸念する声も増加しています。
この記事では、テレワークにおける生産性低下の要因を明らかにし、具体的な解決策までを網羅的に解説します。最新のデータや事例、実践的なツールの紹介も交え、テレワーク時代における生産性向上のヒントを提供します。
目次
データから見るテレワークの生産性
よくある生産性低下の要因
テレワークで発生しやすいコミュニケーションの課題
業務環境の課題
評価制度の見直し不足
IT基盤の未整備
業務効率化のためのツールを活用
コミュニケーションの改善に役立つツールの導入
勤怠管理と働きやすさへの配慮
『Eye“247” Work Smart Cloud』で変えられる生産性
働き方を可視化しデータとして客観的に判断できる
直感的な操作が可能
導入企業様のお声
■テレワークで生産性が低下する本当の理由
テレワーク導入後に「思ったより成果が上がらない」「社員のパフォーマンスにムラが出る」といった声をよく耳にします。これは単なる勤務形態の変化によるものではなく、企業の準備不足や管理手法の見直しが追いついていないことが大きな原因です。
データから見るテレワークの生産性
2020年に実施されたレノボの国際調査によると、在宅勤務の方がオフィス勤務よりも生産性が高まったと回答した割合は、世界全体の平均で63%に上りました。
一方で、「在宅勤務によって生産性が下がった」と回答した割合は、世界平均では13%と少数にとどまりましたが、日本では40%に達し、調査対象となった10か国(日本、米国、ブラジル、メキシコ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、中国、インド)の中で最下位という結果でした。

※出典:レノボ・ジャパン「国際調査 テクノロジーと働き方の進化」 https://news.lenovo.com/pressroom/
●テレワークの生産性が低いと言われていた要因
2020年に実施されたレノボの国際調査によると、コロナ禍における在宅勤務の開始にあたって、IT機器やソフトウェアなどに支出した金額は、調査対象10か国の平均が273ドルだったのに対し、日本は132ドルと最も低い水準でした。
この結果を踏まえ、同調査では、日本で在宅勤務の生産性が低い要因のひとつとして、企業によるテクノロジー投資の不足が挙げられています。

※出典:レノボ・ジャパン「国際調査 テクノロジーと働き方の進化」 https://news.lenovo.com/pressroom/
●近年テレワークに適応できた会社では生産性が向上
日経BP総合研究所 イノベーションICTラボが実施した「働き方改革に関する動向・意識調査」によると、テレワークによる生産性について「生産性が下がった」と回答した人の割合は、過去最低の33.2%にまで減少しました。

※出典:日経BP 総合研究所 イノベーションICTラボ「働き方改革に関する動向・意識調査」
コロナ禍でテレワークが急速に広がった当初は、法整備が不十分であり、企業側の環境整備も追いついていない状況でした。そのため、多くの人が「テレワークでは生産性が下がった」と感じていました。
しかし、2025年現在では関連する法制度も整い、テレワーク環境の整備に本格的に取り組んだ企業では、業務効率化ツールの導入などにより、むしろ従来よりも高い生産性を実感するケースが増えています。 一方で、テレワークにうまく適応できなかった企業では、出社回帰の動きが強まっており、企業間での対応力の差が明確になりつつあります。
●生産性向上の意識が高いのはテレワーカー
近年では、テレワークを積極的に導入する企業と、出社回帰を進める企業とで二極化が進んでいます。
日本生産性本部が実施した「働く人の意識調査」によると、テレワーカーと非テレワーカーを対象に、職場における生産性向上の取り組みの実施状況を比較した結果、すべての項目でテレワーカーの方が非テレワーカーを上回るという傾向が明らかになりました。

※出典:日本生産性本部「第16回 働く人の意識調査」 https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/16th_workers_report.pdf
よくある生産性低下の要因
テレワークで生産性が下がる主な要因は、コミュニケーションの減少や業務進捗の把握の難しさ、業務環境の未整備、評価制度の不透明さ、ITインフラの不備などが挙げられます。
特に、在宅勤務では仕事とプライベートの切り分けが難しく、集中力の維持が課題となるケースも多いです。また、オフィスと比べて情報共有が遅れたり、孤独感や不安感が生じやすい点も生産性低下の一因です。
原因カテゴリ | 主な内容 | 企業側の課題 |
|---|---|---|
コミュニケーション不足 | チーム内での報連相が減る、意思疎通のズレ | 会議の頻度や情報共有の設計不足 |
業務の可視化不足 | 誰が何をしているか見えにくい | タスク進捗や成果の管理が曖昧 |
モチベーション低下 | 孤独感、帰属意識の低下 | 社員との接点の希薄化や評価制度の未整備 |
環境整備の不十分さ | 自宅の作業環境が劣悪、ネット接続不安定 | 業務環境の支援が不十分 |
勤怠管理・労働時間の曖昧さ | サボりや長時間労働の見逃し | 勤務実態の把握不足 |
■コミュニケーションの遮断が信頼と生産性に直撃
テレワーク導入により、社員同士が物理的に離れて働くことになったことで、ちょっとした雑談や声掛けがなくなり、信頼関係の構築が困難になるケースが増えています。特に上司・部下間の連携不足は、業務の方向性のズレやモチベーション低下を招き、生産性にも悪影響を与えかねません。
テレワークで発生しやすいコミュニケーションの課題
テレワークでは、メールやチャット、オンライン会議などのデジタルツールが主なコミュニケーション手段となりますが、これらには限界もあります。たとえば、非言語情報(表情や声のトーンなど)が伝わりにくく、誤解やすれ違いが生じやすいです。
また、気軽な相談や雑談が減ることで、チームの一体感や信頼関係が損なわれることもあります。
コミュニケーションの頻度や質が個人差によって大きく異なるため、情報格差が生まれやすい点も課題です。
報告・連絡・相談の減少
テレワークでは顔を合わせた自然な会話が減るため、報告や相談のタイミングを逃しがちになります。これにより情報の共有が滞り、業務の遅延や誤解を招く原因になります。
孤独感・疎外感の増加
同僚との雑談やちょっとしたやりとりがなくなることで、社員が孤独を感じやすくなります。孤立感が強まると、仕事へのモチベーションやチームへの帰属意識も低下しやすくなります。
曖昧な指示・誤解の発生
文章での指示や伝達が中心になるテレワークでは、ニュアンスが伝わりづらく、意図しない解釈をされることがあります。結果としてミスや再作業が発生し、生産性に影響を与えます。
■環境・評価制度・IT基盤の整備がまだ不十分
テレワークの導入は一見進んでいるように見えても、実際には業務環境や評価制度、ITインフラの整備が追いついていないケースが少なくありません。これらの整備不足は、従業員の生産性やモチベーションの低下を招く大きな要因となります。
業務環境の課題
テレワークにおいては、静かな作業スペースや十分な作業設備(例:デュアルモニター、オフィスチェア)が確保されていない社員も多く、集中力の維持が難しい状況です。また、ネットワークの不安定さやセキュリティ面の不安も、業務の効率化を妨げる大きな課題です。
評価制度の見直し不足
テレワーク下では、成果主義への移行が求められる一方で、多くの企業が従来通りの「勤務態度」や「勤務時間」による評価を続けているため、従業員の不満や不信感を招いています。評価基準が曖昧なままだと、上司と部下の間で不信感が生まれやすく、チーム全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。テレワークに最適化された評価制度の導入が急務です。
IT基盤の未整備
セキュリティを保ちつつ、社員が円滑に業務を進められるITツールやシステムの導入は、テレワークにおいて不可欠です。VPNやログ管理、業務可視化ツールが不十分な状態では、マネジメント層の管理負担が増大し、従業員側も安心して働けません。
また、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクも高まるため、IT基盤の整備は企業にとって最優先課題の一つです。適切なツール選定と教育が求められます。
■生産性向上のための実践的な対策法

テレワークの生産性を高めるためには、業務効率化ツールの活用やコミュニケーションの改善、勤怠管理の工夫など、具体的な対策が必要です。企業は従業員の働きやすさを重視しつつ、IT基盤や評価制度の見直しも進めることで、テレワークでも高い生産性を維持できます。以下に実践的な対策を整理しました。
業務効率化のためのツールを活用
業務効率化には、タスク管理やプロジェクト管理ツールの導入が効果的です。これにより、進捗状況の可視化やタスクの優先順位付けが容易になり、チーム全体の生産性向上につながります。
また、クラウドストレージやドキュメント共有ツールを活用することで、情報の一元管理や共同作業もスムーズに行えます。それにより、作業の優先順位が明確になり、効率的な業務遂行が可能になります。
コミュニケーションの改善に役立つツールの導入
テレワークでのコミュニケーション不足を解消するためには、チャットやビデオ会議ツールの活用が不可欠です。リアルタイムでの情報共有や、気軽な相談・雑談の場を設けることで、チームの一体感や信頼関係を維持できます。情報共有の質も上がり、認識のずれやストレスの軽減にもつながります。また、オンラインホワイトボードやアンケートツールを使うことで、アイデア出しや意見集約も効率的に行えます。
勤怠管理と働きやすさへの配慮
テレワークでは、自己管理が求められるため、勤怠管理ツールの導入や柔軟な勤務時間制度の整備が重要です。また、従業員の健康やメンタルヘルスにも配慮し、定期的な面談やサポート体制を整えることで、安心して働ける環境を作ることができます。働きやすさを重視することで、長期的な生産性向上が期待できます。
加えて、テレワークの際の在宅手当や備品支給制度の導入により、働く環境を物理的に整えることで、従業員満足度が向上し、離職防止やパフォーマンス向上につながります。
■ 『Eye“247” Work Smart Cloud』で変えられる生産性
テレワークの生産性向上を目指す企業にとって、業務の可視化や効率化を支援するITツールの導入は不可欠です。『Eye“247” Work Smart Cloud』は、働き方の見える化や直感的な操作性を強みとするテレワークの課題解決に役立つクラウドサービスです。
働き方を可視化しデータとして客観的に判断できる
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、従業員のPC操作や業務時間、作業内容を自動で記録し、働き方をデータとして可視化します。これにより、上司や人事担当者は客観的なデータに基づいて業務状況を把握でき、評価や業務改善の根拠とすることが可能です。また、従業員自身も自分の働き方を振り返ることで、自己管理や業務効率化の意識が高まります。
直感的な操作が可能
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、シンプルで分かりやすいインターフェースを採用しており、ITリテラシーに自信がない方でも簡単に使いこなせます。複雑な設定や操作が不要なため、導入後すぐに現場で活用できるのが大きな魅力です。また、管理者・従業員双方の負担を軽減し、業務効率化を後押しします。
導入企業様のお声
管理画面が軽量でサクサク動き、UIも比較的親切で分かりやすいです。 なにより、他社の類似製品と比較にならないほど安価なので 「まず試す」がしやすいのは大きなメリットだと思います。 安価でいて機能も必要十分なので、不満が少ない良い製品だと思います。 ITreviewより |
テレワーク時の生産性の向上に一番役に立ちました。またチームごとで各メンバーが何に時間が一番かかっているかを簡単に把握できますので、マネジメントツールとしても効果的だったと思います。 ITreviewより |
リモート業務の管理をする製品を導入するために20製品ほどを比較検討しました。選考ポイントは、2点あり、業務内容の把握とセキュリティ対策でした。この2点を実装している製品は少ないのですが、そのなかでクオリティの高さとコストの安さを兼ね備えているのがEye247でした。一般的にクオリティが高ければ、それに応じてコストも高くなるのが普通ですが、Eye247は見事にその両方を兼ね備えています。20製品ほどを調査しましたが、導入すべきはEye247しかないと絶対の自信がありました。 ITreviewより |
■まとめ:テレワークの生産性向上は見える化と仕組みづくりが重要
テレワークの生産性低下には、コミュニケーション不足や業務環境・評価制度・IT基盤の未整備など、さまざまな要因が絡み合っています。しかし、適切なツールの導入や評価制度の見直し、働きやすさへの配慮を徹底することで、テレワークでも高い生産性を実現することは十分可能です。
『Eye“247” Work Smart Cloud』のような業務可視化ツールを活用し、データに基づいた改善を進めることで、テレワークにおける生産性の質を一段階引き上げましょう。
この記事のポイント
|