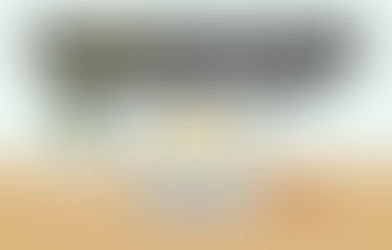業務効率とは結局“データ”で決まる!定義・指標・改善ステップを徹底解説
- FuvaBrain
- 2025年5月23日
- 読了時間: 12分

働き方の多様化とDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する今、限られたリソースで最大の成果を出すためには“勘と経験”ではなく“データ”を活用した業務効率の可視化と改善が不可欠です。
この記事では、業務効率の基本概念から具体的な測定指標、改善のための実践ステップまでを網羅的に解説します。
目次
労働生産性(付加価値 ÷ 労働投入量)
タクトタイム/リードタイム
稼働率・設備総合効率(OEE)
ムダな会議・承認フロー
情報共有の属人化・サイロ化
アナログ作業・二重入力
システムの老朽化・ツール乱立
過剰・不足リソース配置
プロセスマッピングでムダを可視化
RPA・AIで定型業務を自動化
クラウドツール統合で重複作業削減
OKR/KPIによる目標管理
ナレッジ共有と標準化
働き方の柔軟化(ハイブリッドワーク)
データドリブンPDCAサイクル
■業務効率とは?基本概念と重要性をわかりやすく解説
業務効率とは、時間・人員・コストなどに対してどれだけ大きな成果や付加価値を生み出せたかを示す指標であり、無駄を省き、時間を短縮し、生産性を高めるための取り組みです。 企業が限られたリソースで最大の成果を上げるためには、業務効率の定義を明確にし、継続的な改善サイクルを回すことが重要です。特にDXや働き方改革が叫ばれる今、業務効率の向上にはデータを活用し、改善点を洗い出すことが効果的であり、業務効率の改善・向上が企業競争力を左右すると言っても過言ではありません。
■業務効率を数値化する3つの代表的指標
業務効率の改善には、現状を正確に把握することが不可欠です。そのためには、業務効率を「見える化」し、客観的な数値として評価できる指標を活用する必要があります。
ここでは、代表的な3つの指標を紹介し、それぞれの意味と活用方法について詳しく確認していきます。これらの指標を導入することで、自社の業務効率をデータで把握し、具体的な改善アクションにつなげることが可能になります。
労働生産性(付加価値 ÷ 労働投入量)
労働生産性は、企業が投入した労働時間や人員に対して、どれだけの付加価値(売上高-外部購入費など)を生み出したかを示す指標です。この数値は、労働の効率性を定量的に把握するうえで非常に重要であり、国際比較や部門間比較などにも広く用いられています。経営層が全社レベルで課題を把握する際に有効です。 たとえば、ある部門の付加価値が高いにもかかわらず労働時間が過剰であれば、業務の進め方に改善の余地があると判断できます。経営層が全社レベルでパフォーマンスを評価し、適切なリソース配分や報酬制度の見直しを行うための基礎データとして活用されます。
タクトタイム/リードタイム
製造業で広く使われる指標ですが、タクトタイムとリードタイムは、業務プロセスのスピードと効率性を測定するうえで欠かせない指標です。タクトタイムとは、「一定の需要を満たすため、1つの製品を仕上げるのに使える理想的な時間」を意味し、生産のリズムを定義するのに使われます。一方、リードタイムは「顧客が注文してから製品やサービスが提供されるまでの所要時間」を示し、顧客満足度と密接に関わります。 これらの数値を定期的に分析することで、工程のどこに無駄が生じているかを明確化し、プロセスの再設計やボトルネックの解消に役立てることができます。製造業はもちろん、IT業界やコールセンターなどでも応用可能です。
稼働率・設備総合効率(OEE)
稼働率とOEE(Overall Equipment Effectiveness/設備総合効率)は、機械や設備の稼働状況を把握する指標で、製造ラインのボトルネックや機器の維持コストの最適化に役立ちます。
稼働率は、設備が実際に稼働していた時間の割合を示し、遊休状態や停止時間の多寡を測るのに役立ちます。
OEEは稼働率に加え、性能効率(実際の生産スピードが理想速度にどれだけ近いか)と品質歩留まり(製品のうち不良品の割合)を掛け合わせた複合指標です。たとえば、稼働率が高くても不良率が高ければOEEは下がるため、単なる稼働時間では測れない“実効性”を可視化できます。これらのデータを分析することで、定期点検の見直しや、生産計画の最適化に活かすことが可能です。
■業務効率が低下する5つの典型要因

業務効率を高めるには、まず非効率を生む根本的な要因を知ることが重要です。企業の日常業務において見落とされがちな“ムダ”や“手間”は、少しずつ蓄積し、大きな時間損失やコスト増加へとつながっていきます。ここでは、特に多くの企業が直面している5つの典型的な業務非効率の要因について確認してきます。
ムダな会議・承認フロー
不要な会議や過度な承認プロセスは、社員の生産性を著しく低下させます。特に、目的が曖昧な定例会議や、多段階の承認フローは意思決定のスピードを鈍化させる要因です。これにより、プロジェクトの遅延や社員のストレス増加にもつながります。会議は本当に必要か、出席者は適切か、議題と成果物が明確かといった観点で精査し、会議の質を見直すことが求められます。オンライン会議では、録画機能や議事録の要約共有を通じて参加人数を最適化する工夫も重要です。
情報共有の属人化・サイロ化
情報が個人や部署に閉じたままだと、重複作業や意思決定の遅延が生まれます。情報が一部の担当者や特定部門に集中すると、業務の属人化が進み、他部門との連携が滞る原因になります。
たとえば、担当者が不在の際に業務が停滞したり、同じ資料が複数部門で重複作成されたりといった非効率が発生します。ナレッジマネジメントツールやグループウェアを導入し、業務マニュアルや進捗状況を社内ポータルで一元管理することで、サイロ化を防ぎ、横断的な連携を促進できます。
アナログ作業・二重入力
紙媒体による申請書や手書き伝票、複数システムへの同一データの重複入力は、手間がかかるだけでなくヒューマンエラーの温床でもあります。申請ワークフローの電子化や、異なるシステム間のAPI連携を通じて、手作業を排除することが効率化の鍵です。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入も効果的で、人的ミスの削減と処理スピードの向上を同時に実現できます。
関連記事:
システムの老朽化・ツール乱立
古い基幹システムは、最新のクラウドサービスやアプリケーションとの連携が難しく、IT部門の保守負担やセキュリティリスクも高まります。さらに、現場主導で個別に導入されたツールが乱立すると、データの一元管理が困難になり、情報の整合性が失われます。システムのリプレイスや統合、SaaSの標準化により、全社的な情報基盤を整備し、スムーズなデータ連携と運用の統制が図れます。
過剰・不足リソース配置
人員の過不足は、企業のコスト効率や社員のワークライフバランスに直結する重大な課題です。業務量に対して人手が多すぎるとコストが増加し、逆に少なすぎると残業や納期遅延が発生します。属人的な判断ではなく、業務ログや稼働率、プロジェクトの進捗データに基づいた定量的な分析により、最適な人員配置とリソース計画を立てることが重要です。
■業務効率を劇的に改善する7つのステップ

業務効率を改善するためには、単なる作業スピードの向上だけでなく、プロセス全体の最適化や組織全体の生産性向上を目指す必要があります。ここでは、現場で実践可能な7つの具体的な改善施策を紹介します。どの企業でも共通して取り組める内容ばかりなので、自社に合ったものから導入していくことが可能です。
プロセスマッピングでムダを可視化
業務プロセスの全体像を可視化することで、どの工程にムダや非効率が潜んでいるかを明らかにできます。 たとえば、申請業務において同じ情報を複数の帳票に転記していたり、複数部門をまたいだ承認ルートに時間がかかっていたりするケースでは、業務フローを図式化(フローチャート化)し、関係者間で共通認識を形成することが、改善の出発点となります。さらに、改善前後でフローを比較することで、成果の定量化も可能になります。
RPA・AIで定型業務を自動化
請求書処理やデータ集計など、定型的でルールベースな業務をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIで自動化することで、大幅な工数削減が期待できます。これにより、単純作業にかかっていた人的リソースを、顧客対応や企画立案といった付加価値の高い業務へと振り分けることができます。
クラウドツール統合で重複作業削減
多くの企業が複数のSaaSツールを利用している中で、データの一元管理が難しくなっています。SaaS統合プラットフォームを活用することで、ID・パスワードの統合、ワークフローの自動連携、ファイル共有の最適化が実現します。結果として、同じデータを複数のツールに手入力したり、確認のために何度もアプリを行き来したりする無駄を排除できます。IT資産の管理面でもセキュリティ強化が図れます。
OKR/KPIによる目標管理
OKR(Objectives and Key Results)やKPI(Key Performance Indicators)は、目標達成の進捗を可視化し、業務の優先順位を明確にするための指標です。OKRでは「何を目指すか(O)」と「どうやって測るか(KR)」を明確に定義するため、部門横断的な連携やイノベーション推進にも効果的です。KPIは業務の中間目標として、現場レベルでの改善状況をモニタリングできます。両者を併用することで、戦略と現場のアクションを結び付ける強力なマネジメント手法となります。
ナレッジ共有と標準化
属人化した業務の引き継ぎや教育を円滑に進めるためには、ノウハウや手順を組織で共有・標準化する仕組みが必要です。社内ポータルやナレッジベースに、FAQ、操作マニュアル、トラブル対応例などを蓄積していくことで、新入社員や異動者の立ち上がりも早くなります。また、検索性やアクセス性を高めるため、メタデータ付与やタグ管理も重要になります。
働き方の柔軟化(ハイブリッドワーク)
在宅勤務と出社勤務を組み合わせるハイブリッドワークは、社員の働きやすさと業務の効率性を両立する手段です。例えば、集中力を要する作業は在宅で、対面によるチームミーティングは出社で行うといった使い分けが可能です。オフィススペースの有効活用や、遠隔地人材の登用にもつながるため、戦略的人事にも貢献します。ただし、出退勤管理や業務進捗の可視化など、柔軟な働き方を支えるITインフラの整備が不可欠です。
データドリブンPDCAサイクル
業務改善を感覚や属人的判断に頼るのではなく、データに基づいて行うことが「データドリブンPDCA」です。たとえば、日々の業務ログから「誰が、いつ、何の作業に、どれくらいの時間をかけたか」を可視化し、非効率なプロセスを特定。次に改善案を立て、実行・評価・修正を繰り返すことで、継続的な改善サイクルを構築できます。BIツールやダッシュボードを活用すれば、リアルタイムでの進捗管理や異常検知も可能です。
■『Eye“247” Work Smart Cloud』導入で業務効率が改善した事例3選
PCログデータをもとに業務を可視化し、業務効率を向上させる『Eye“247” Work Smart Cloud』を導入したことにより、業務効率が改善した企業さまの事例を3選ご紹介いたします。
PC業務中心部署の業務を可視化したいとの意見があり、業務可視化ツールの導入を検討。『Eye“247” Work Smart Cloud』導入後は、実際に予想していたよりもメールやExcelの業務が多く、メールの業務に関してはCcに入れる社員を定めておらず多くの社員がCcに入れられることが常態化しており、本当に重要なメールに気づかなかったり、業務の遅延や業務効率化の妨げになっていたりすることが分かりました。
その後、メールのルールを定め本来の業務に専念してもらえることができ、生産性・業務効率の向上につながりました。
コロナ禍においてテレワークを実施した際、業務状況に不安を感じるようになり、『Eye“247” Work Smart Cloud』の導入を検討。『Eye“247” Work Smart Cloud』導入後は、「PC操作ログ」を見ることでテレワークでも生産性を意識した業務をしていることが分かり、安心することが出来ました。また、今までよりも社員マネジメントができる環境が整い、会社としても労働生産性を意識した人材育成のきっかけになりました。
ログの内容を業務効率化する際、すでに利用していたログ管理ツールでは海外拠点社員の業務時間が時差を考慮されないまま取得されており、新しいログ管理ツールの導入を検討。『Eye“247” Work Smart Cloud』導入後は、工数管理ツールの内容と『Eye“247” Work Smart Cloud』で取得したPCログの内容を比較することで、適切な業務が行われているかどうかを確認し、機械的に業務上の問題を見つけ出すことが可能になりました。
本当に問題のある箇所をクリティカルに修正する対応を取れるので、適切な業務遂行につながりました。
■業務効率向上を支援する『Eye“247” Work Smart Cloud』
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、PC操作ログやアプリ利用状況、ファイル操作履歴をリアルタイムで収集・可視化するクラウドサービスです。業務の稼働状況をヒートマップやレポートで確認できるため、ボトルネックの発見と改善策の実行を迅速に行えます。
『Eye“247” Work Smart Cloud』では、PC操作ログにより、「いつ・だれが・どのような」作業を行っていたのかを把握することができます。
PC操作ログを確認することで、社員の作業内容を把握し、業務量が過多になっていないか業務が属人化されていないか、業務の偏りや業務内容の傾向を知ることができ、業務効率改革の手伝いになります。また、業務を可視化することで単純な業務や頻発しているアナログ業務を見つけ、ツールや自動化への変更を検討する生産性向上のきっかけになります。
PC操作ログと勤怠打刻データを並べて確認する勤怠乖離チェックの機能を活用することで、管理者は隠れ残業やサボりを見つけることができます。サボりや隠れ残業がありそうな部分はアラート表示でひと目で確認でき、業務改善やヒアリングにより未然にトラブルを防ぐことが可能です。
■まとめ:業務効率を高めて組織競争力を向上させる
業務効率はデータで測定し、データで改善する時代です。定量指標を設定し、改善施策を継続的に実行することで、生産性と社員満足度を同時に向上させましょう。『Eye“247” Work Smart Cloud』を活用すれば、業務の見える化と改善スピードが飛躍的に高まります。