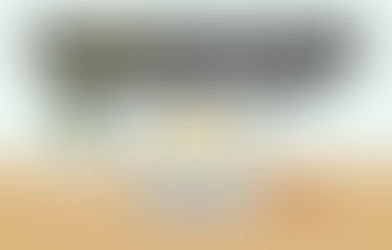PCログと勤怠に乖離が生じる本当の理由とは。防止策7選
- FuvaBrain
- 7月24日
- 読了時間: 10分
更新日:2025年7月24日

近年、客観的な労働時間管理が求められる中で「PCログと勤怠の乖離」は大きな課題となっています。PCログと打刻時間に差が生じる原因やリスクを理解し、乖離を防ぐ仕組みを整えることは、適切な勤怠管理と従業員の安心を守るために不可欠です。
この記事では、乖離の理由や具体的対策を詳しく解説します。
目次
打刻と実際の業務開始・終了のズレ
スリープ・起動・シャットダウンとアクティビティログの盲点
テレワーク環境での労働時間の自己申告制
管理システムやツールの運用ミス・設定ミス
従業員による言い訳・意図的な不正操作のケース
労働基準法違反・違法リスクと企業責任
給与計算・残業代支払いミスの実例
IPO・実態調査・労務監査時の指摘事例
従業員間・人事間の信頼関係悪化
PCログと勤怠データの照合作業のポイント
ケース別に分類する
実態調査・ヒアリング
システム・ツールの適切な導入と活用
タイムカード・アクティビティログなど多角的記録の導入
打刻操作の徹底・従業員教育
管理者による定期的なチェック体制の強化
乖離発生時の対処法・対応マニュアルの整備
社労士・専門家による労務支援の活用
働き方改革やガイドラインをふまえたルール作成
PCログと勤怠の乖離を発見する『Eye“247” Work Smart Cloud』
勤怠乖離チェック
■PCログと勤怠データの乖離とは
「PCログと勤怠データの乖離」とは、タイムカードや日報などの勤怠データとPCの操作ログとの間に、業務開始・終了時間などで食い違いが生じることを指します。
働き方改革関連法や厚生労働省のガイドラインでも、PCログや入退室記録など客観的記録を基に労働時間を把握することが求められているなか、PCログと勤怠データの乖離は労務リスクの原因になります。
■PCログと勤怠データに乖離が発生する主な理由
PCログと勤怠データが乖離する理由を正しく把握することは、適切な勤怠管理の第一歩です。
乖離が発生する主な理由は、
打刻と実際の業務開始・終了時間のズレ
スリープ・起動・シャットダウン
テレワーク・自己申告制の課題と改ざんリスク
管理システムやツールの運用ミス・設定ミス
従業員による言い訳・意図的な不正操作
の5つに分類されます。
乖離が起こる原因を知ることで、再発防止や対策検討がしやすくなります。
打刻と実際の業務開始・終了時間のズレ
出退勤打刻は早く打っていても、実際のPC操作開始は遅いなど、打刻時間と実働時間に差が生じるケースがあります。通勤途中にスマホで打刻しているなど、物理的に勤務が開始していない事例もあります。こうした乖離を放置するとサービス残業や不正申告の温床になります。
スリープ・起動・シャットダウンとアクティビティログの盲点
PCを起動したまま放置したり、スリープ・シャットダウンを誤操作したりすると、アクティビティログに実作業が反映されない場合があり、正確に記録されません。たとえば、退勤時間前にPCを起動したまま席を離れた場合、労働時間が長く記録されてしまいPCログと勤怠データの乖離が発生します。
テレワーク環境での労働時間の自己申告制
テレワーク環境では上司の目が届きにくく、自己申告に頼りがちで、勤怠管理では正確性が損なわれやすくなります。中には打刻時刻を後から修正するなど、意図的な改ざんが行われるリスクもあります。
管理システムやツールの運用ミス・設定ミス
PCログ収集ツールや勤怠管理ツールの設定不備・運用ミスにより、正確なログが取得できないことがあります。ログの抜けや誤記録など、運用ルールを怠れば、意図せず乖離を招く要因になります。
従業員による言い訳・意図的な不正操作
「PCの起動に時間がかかった」「PCが固まって起動できなかった」「打刻を忘れた」などを装い、本人の責任範囲で乖離が発生しても言い訳される場合があります。中にはPCを操作せずに勤務しているように見せかける不正もあります。
■PCログと勤怠の乖離が及ぼすリスク・問題点
PCログと勤怠データ間に乖離がある状態を放置すると、企業にはさまざまなリスクが生じます。単なるデータのズレと捉えるのではなく、法的責任や内部統制の信頼性、従業員との関係性にも深く関わる問題として捉える必要があります。
労働基準法違反・違法リスクと企業責任
PCのログと勤怠時間の乖離を放置したまま、未払い残業や長時間労働が常態化すれば、労働基準法違反として是正勧告や罰則を受けるリスクがあります。訴訟や労働審判に発展するケースもあり、企業の信用を大きく損なう可能性があります。
給与計算・残業代支払いミスの実例
実際に乖離により残業代が過少支給され、過去に遡って支払うよう命じられた事例が多くあります。残業時間の計算ミスや、未払い賃金の発生、誤った時間管理は労使間のトラブルの元になります。
IPO・実態調査・労務監査時の指摘事例
IPO準備段階で勤怠データの齟齬を監査法人から指摘され、上場スケジュールが遅延したケースがあります。企業統治体制に対する信用低下や、問題の指摘を受けるリスクがあります。
従業員間・人事間の信頼関係悪化
PCログと勤怠データの乖離が続き、長期化すると「上司が残業を黙認している」「従業員が不正に勤怠を申告している」と疑念を持たれ、信頼関係が崩れる恐れがあります。互いに疑心暗鬼となり、職場のモチベーション低下を招きます。
■乖離発生時のチェック・調査方法

PCログと勤怠データに乖離が発生した際には、その背景を正確に把握し、適切な対応を取ることが重要です。単なる記録のズレではなく、システム運用や従業員の行動、職場環境など複数の要因が関係していることが多いため、丁寧な調査が求められます。ここでは、チェックの観点や調査のステップについて解説します。
PCログと勤怠データの照合作業のポイント
まず、PCログ(起動・操作・終了時間など)と打刻記録(出勤・退勤時間)を突き合わせ、具体的にどの時間帯に乖離が生じているのかを確認します。特に出勤直後や退勤直前にズレが生じやすいため、時間帯別のパターン分析が重要です。また、照合は単発でなく週次や月次単位で継続的に行うことで、傾向を把握しやすくなります。PCログの整合性が取れていない場合は、再取得や再確認も検討すべきです。
ケース別に分類する
「打刻後に私用対応で業務を始めていなかった」「PC起動後に会議準備をしていた」「退勤打刻後も資料作成など業務を行っていた」など、ケース別に理由と対応策を整理し、テンプレート化をしておくと調査や発覚時の初動の対応が効率化します。
実態調査・ヒアリング
本人へのヒアリングは事実確認に有効です。乖離が認められた場合、まずは当該従業員本人へのヒアリングを行い、乖離の背景を丁寧に確認します。ヒアリング内容は記録として管理台帳等の資料に保存し、担当者・日付・対応内容を明記しておくことが重要です。また、事実確認後は必要に応じて関係部門とも連携し、再発防止に向けた職場ルールの見直しや教育を実施することが効果的です。
■PCログ・勤怠の乖離を防ぐ実践的防止策7選
PCログと勤怠データの乖離を防ぐには、単なる記録の取得にとどまらず、日々の運用とルール設計の見直しが欠かせません。ここでは、具体的にどのような対策を講じれば乖離を最小限に抑えられるのか、実務で有効な以下の7つの方法を紹介します。
システム・ツールの適切な導入と活用
タイムカード・アクティビティログなど多角的記録の導入
打刻操作の徹底・従業員教育
管理者による定期的なチェック体制の強化
乖離発生時の対処法・対応マニュアルの整備
社労士・専門家による労務支援の活用
働き方改革やガイドラインをふまえたルール作成
現場への定着を意識した実践的なポイントを解説します。
システム・ツールの適切な導入と活用
PCログ管理ツールや勤怠連携システムを導入し、客観的なデータで出退勤の記録を裏付けることが重要です。これにより、自己申告ベースのあいまいな勤怠から脱却し、信頼性の高い勤怠管理が実現できます。また、ツール導入だけでなく、社内での定着と活用を促すために、導入後の運用ルールや従業員の教育体制も合わせて整備しましょう。
タイムカード・アクティビティログなど多角的記録の導入
PCログだけでなく、入退室記録や業務アプリの利用履歴など、複数の客観的記録を組み合わせることで、乖離リスクを最小化し、乖離の特定精度が向上します。これにより、特定のログが欠損した場合でも、他の情報で補完できるため、より正確な状況把握が可能になります。
打刻操作の徹底・従業員教育
従業員に対して正しい打刻ルールの教育を行い、マニュアルや研修で定着させることが不可欠です。特に「打刻=勤務開始」「PC起動=業務開始」といった概念の違いを明確に伝えることで、誤解やルール逸脱を防ぎます。
管理者による定期的なチェック体制の強化
日々のチェックではなく、月次・四半期など定期的な分析で、PCログと勤怠データの乖離傾向を早期発見します。ログのパターンや傾向を可視化するダッシュボードを活用することで、効率的にチェックできる体制を構築しましょう。
乖離発生時の対処法・対応マニュアルの整備
乖離を検知した際に迅速かつ的確に対応できるよう、対応フローをマニュアル化しておくことが求められます。例外パターンや従業員への聞き取り方法、対応の記録方法などを具体的に文書化しておくことで、属人的な対応を防ぎ、組織全体での統一的な対応が可能になります。
社労士・専門家による労務支援の活用
勤怠や労働時間の問題は、法的な判断や対応が求められる場合も多くあります。社会保険労務士などの専門家と連携し、制度設計や運用改善を進めることで、内部リソースだけでは対応しきれない部分を補完し、法令遵守と運用安定性を両立できます。
働き方改革やガイドラインをふまえたルール作成
厚生労働省のガイドラインなどを参考に、自社の業種や勤務形態に即した勤怠ルールを設計しましょう。ルールは単に形式を整えるのではなく、現場の実情に合わせて実効性のある内容にし、定期的に見直すことが重要です。
■PCログと勤怠の乖離を発見する『Eye“247” Work Smart Cloud』
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、PC操作ログを自動で取得・分析し、勤怠データと比較することで乖離を把握できます。乖離が発生した場合も詳細なログで原因を特定でき、適切な対応が可能です。
『Eye“247” Work Smart Cloud』の勤怠乖離チェックを活用することで、PC操作ログの時間と勤怠データの時間をひと目で比較でき、乖離が発生しているかどうかを確認することが出来ます。 隠れ残業や休日出勤があるか、サボりの発生まで知ることができます。
また、勤怠乖離アラート※により、基準時間以上の乖離があった場合には、アラート機能で管理者に連絡が届きます。
※勤怠乖離アラート管理者通知を使用する場合は、「勤怠管理オプション」の契約が必要です。
※勤怠打刻のデータは、他社ツールのデータをCSVで取込むことも可能です。
▼「勤怠乖離チェック」実際の画像

■まとめ:勤怠管理のあるべき姿
PCログと勤怠データの乖離は、放置すれば労務リスクだけでなく信頼関係にも悪影響を与えます。乖離を正しく把握し、適切な仕組みやツールで管理することが、従業員の安心と企業のコンプライアンスを守る第一歩です。
この記事のポイント
|