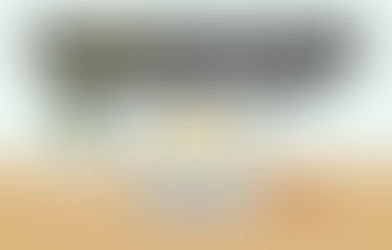職場が暑すぎる!オフィスの熱中症・暑さ対策にテレワークを導入
- FuvaBrain
- 7月22日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年7月22日

夏になると多くの企業で「職場が暑すぎる」という悩みが聞かれるようになります。地球温暖化や都市のヒートアイランド現象により、オフィスや工場の室温が異常に上昇し、従業員の健康や業務効率に深刻な影響を与えかねません。特に、空調設備が古い建物や換気が十分でない職場では、熱中症リスクが高まります。
この記事では、暑すぎる職場が引き起こす問題や、効果的な対策として注目されるテレワークの活用方法について解説します。
目次
生産性への影響
熱中症
離職につながる
労災認定・法的責任
夏の理想の働き方
熱中症特別警戒アラートによりテレワーク推奨
今後の法改正や実態調査をチェック
夏の出社・職場環境の見直し
勤務時間帯の柔軟な調整(早朝出勤や時差出勤)
定期的な休憩の義務化
空調設備の見直し・増強
冷感グッズや水分補給の促進
温湿度センサーなどによるモニタリング
『Eye“247” Work Smart Cloud』で暑い夏もテレワークで快適に!
業務の見える化で成果管理が可能
テレワークの情報漏洩リスクも管理
データに基づく勤怠管理で法令順守を支援
テレワーク中の熱中症発見にもつながる
導入企業様の口コミ
■猛暑日、暑すぎる職場に潜むリスク
地球温暖化の影響により、夏の猛暑日は年々増加傾向にあります。オフィスや工場などの職場においても室温が高くなり、従業員の健康やパフォーマンスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、暑すぎる職場が抱える主なリスクを紹介します。
生産性への影響
暑さでボーっとすると、集中力が低下し、ミスや業務効率の低下が起こりやすくなります。生産性を向上させるためには、適切な室温で作業をする必要があります。
厚生労働省が定める「事務所衛生基準規則」においては、室温は17~28℃および相対湿度が40%~70%となるように努めなければならないと定められています。また、環境省においては夏の「クールビズ」は室温28℃、冬の「ウォームビズ」は室温20℃が推奨されています。
コーネル大学の人間工学研究によると、室温25℃でタイピングミスは44%減少、タイピングの生産性は150%向上しており、室温25℃前後が最も生産性が高いと言われています。
従業員への聞き取りや、上記のようなデータをもとに、生産性が損なわれることのない適切な室温で作業できるように職場環境を整えることが重要です。
熱中症
屋内でも湿度と室温が高い場合、熱中症になるリスクは大いにあります。軽度であっても健康悪化につながり、重度の場合、特に高齢者や持病を抱える従業員にとっては命に関わる危険も。工場現場や建設現場など高温多湿な場所でも熱中症のリスクがより高くなります。
離職につながる
暑さ対策が不十分で過酷な職場環境が続くと、従業員のモチベーションは低下し、離職につながるケースがあります。働きやすい環境を整備することは、優秀な人材を確保するうえでも重要です。
労災認定・法的責任
熱中症による健康被害が労災として認定されるケースもあります。企業が暑さ対策を怠った場合、安全配慮義務違反として法的責任を問われるリスクがあります。
■テレワークで夏の暑さから従業員を守る
テレワークは、暑さによる健康被害や業務効率の低下を防ぐ有効な手段として注目されています。柔軟な働き方の導入は、従業員満足度や企業イメージの向上にもつながります。
夏の理想の働き方
Job総研が発表した「2025年 夏の働き方実態調査」によると、今夏の出社予定については「出社のみ」「出社多め」「どちらかといえば出社多め」と回答した人が74.6%の過半数を占めていました。
また、さらに出社予定の回答者に出社は会社からの要請なのかを確認したところ、「要請あり」が77.6%、「要請なし」が22.4%でした。

さらに、回答者全体に夏の理想の働き方を調査した結果、「出社したい派」が48.0%、「テレワークしたい派」が52.0%でした。
「出社したい派」の理由を調査したところ、「涼しい環境が整っているから」が最多回答になりました。同じく、「テレワークしたい派」の理由を調査したところ、「外が暑いから」が最多回答になりました。
出社回帰の傾向や物価高によりテレワークの光熱費を節約したい価値観から、2023年の結果よりも出社派が増えたものの、現在でも猛暑日にはテレワークをしたい層が多いようです。
※出典:Job総研「2025年 夏のはたらき方実態調査」
熱中症特別警戒アラートによりテレワーク推奨
暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)とは、気温・湿度・輻射熱を考慮した熱中症リスクの指標です。
この暑さ指数(WBGT)が35以上と予想されると、熱中症特別警戒アラートが環境省より発表されます。
アラートが発表された場合は、前例にない暑さにより、熱中症による重大な被害が生じるおそれがある状況であり、外出を控え、涼しい場所で過ごすことが推奨されます。また、経営者はすべての人が熱中症対策が出来ているかを徹底し、外出や野外イベントの中止、延期、テレワークを含む変更等の対応が必要です。
35以上でなくても、暑さ指数が28を超えると、熱中症患者が著しく増加するため、注意が必要です。
日常生活に関する熱中症予防指針
暑さ指数(WBGT) | 注意事項 |
|---|---|
危険(31以上) | 高齢者においては安静状態でも熱中症が発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
厳重警戒(28以上31未満) | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 |
警戒(25以上28未満) | 運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 |
注意(25未満) | 一般に熱中症の危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |
■職場における具体的な熱中症対策7選

猛暑が常態化する今、職場の暑さは単なる不快さを超えた「安全・健康の課題」となっています。夏季の職場における熱中症対策は、従業員の命と健康を守るために欠かせません。特に空調が不十分な古いオフィスビルや工場では、室温が危険なレベルまで上がることもあります。
企業は熱中症のリスクを減らす取り組みを行うとともに、従業員の働く環境を整備することが求められます。ここでは、企業が果たすべき役割と、現場で実践できる対策について解説します。
今後の法改正や実態調査をチェック
厚生労働省が公表する熱中症対策マニュアルや、労働環境に関する実態調査の動向を定期的に確認することは、企業がとるべき基本姿勢です。たとえば、気候変動の影響を踏まえた労働安全衛生法関連のガイドライン見直しや、テレワーク推奨に関する通達なども見逃せません。最新情報の収集により、法令遵守だけでなく従業員の安全確保にもつながります。
夏の出社・職場環境の見直し
気温や湿度の上昇を踏まえ、「猛暑日は原則テレワーク」「昼間の外勤は避ける」「冷房設備の更新や断熱対策」など、環境に合わせた柔軟な勤務体制が求められます。また、屋外作業のある職場では、休憩時間の拡充や日陰の確保といった具体的な配慮も重要です。
勤務時間帯の柔軟な調整(早朝出勤や時差出勤)
気温が比較的低い早朝に出勤する「朝型勤務」や、通勤時間帯と重ならない「時差出勤」の導入により、日中の猛暑を避ける働き方が可能になります。これにより、通勤ストレスや熱中症のリスクが軽減されるとともに、集中力の高い時間帯に業務を行えるメリットもあります。
定期的な休憩の義務化
暑さがピークになる時間帯を避け、1〜2時間ごとに休憩時間を設ける制度を整えることで、従業員の体調管理とパフォーマンス維持が期待できます。特に午後のピーク時は、10〜15分の短い休憩を設けることで、従業員のリフレッシュと安全確保も期待できます。空調の効いた休憩スペースの整備も効果的です。
空調設備の見直し・増強
老朽化した空調機器の交換や、設置場所の見直しによって、室内の温度を効率よく下げることができます。加えて、定期的なエアコンのフィルター清掃や機器の点検・メンテナンスも欠かせません。最近では、省エネ性と冷房効率を両立する最新機器の導入も効果的です。
冷感グッズや水分補給の促進
業務中でも快適に過ごせるよう、冷却タオルやネッククーラー、ミストファンなどの冷感グッズを従業員に支給するのも効果的です。特に屋外での作業が多い職場においては、命を救うこともあります。また、熱中症予防として、水分補給を促す啓発ポスターの掲示や、ペットボトル飲料やウォーターサーバーの無償提供も有効です。こうした対策により、従業員の自己管理意識も高まります。
温湿度センサーなどによるモニタリング
リアルタイムで室内環境を把握できる温湿度センサーを設置し、一定の基準値を超えた場合にアラートを出すことで、早期に対策を講じることが可能になります。これにより、従業員や管理者が迅速に対応でき、熱中症リスクの高い状況を未然に察知できます。
■『Eye“247” Work Smart Cloud』で暑い夏もテレワークで快適に!
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、従業員のPC操作ログや業務状況を可視化できるクラウドサービスです。オフィスに出社せずとも、働き方の実態を把握・評価できるため、テレワーク中でも適切な労務管理が可能になります。
テレワークを導入する上で、従業員の業務状況の把握が困難であることが課題になっています。そのため、経営者や管理者が従業員の業務状況を把握できる仕組みが必要です。
『Eye“247” Work Smart Cloud』では、PC操作ログにより業務内容を把握することが可能です。1日のうちに「どこで、どのような業務を、どのくらい行っていたのか」を把握でき、さらに1時間ごとの作業内容の確認もできます。
PC操作ログから分かる様々なデータにより、管理者はテレワーク中の正確なマネジメントや適切な評価をすることが可能です。
テレワーク環境下において、PC端末を社外に持ち出すため、ウイルス感染や不正アクセスなどの情報漏洩リスクが高まります。
『Eye“247” Work Smart Cloud』では、テレワーク環境における情報漏洩リスクを可視化し、抑制することも可能です。セキュリティソフトのインストール状態や脆弱性のあるソフトウェアの状況確認、業務に関係ないソフトの起動禁止を行うことで、最低限のセキュリティを保つことができます。
情報資産の持ち出し等の内部不正やヒューマンエラーによる情報漏洩対策としては、個人情報や機密情報などをログにより常に監視することができます。万が一情報の持ち出しがあった際も、「いつ、だれが、どのデータを、どのように操作したのか」が、ログとして残っており、証拠として活用することも可能です。
テレワーク環境下では、隠れ残業や休日出勤などの上司が把握できないサービス残業が発生しやすくなります。特に、自己申告制の勤怠管理では、実際の労働時間と異なった労働時間が申告されやすくなっています。
『Eye“247” Work Smart Cloud』では、テレワーク環境での課題を解決し、適切な労務管理を実現します。
PC操作ログにより実労働時間を把握でき、勤怠乖離チェック機能で打刻データと照合することで、実際の労働時間と申告された勤怠データに乖離がないか、ひと目で確認することができます。
さらに、勤怠オプションを契約することで、オンオフが難しいテレワーク環境下においての小刻みな働き方を支援します。「再開」「中断」などの打刻機能を活用することで、柔軟な労働環境を実現します。
テレワーク中の熱中症発見にもつながる
適切な熱中症対策をしていないと、室内であっても熱中症になるリスクがあります。管理者の目から離れたテレワーク環境下においては、従業員の熱中症対策が正しく行われているかを確認することができません。
『Eye“247” Work Smart Cloud』を活用し、ログ操作履歴閲覧中、PCの操作が長い時間行われていない等に気づくことが出来れば、テレワーク環境下においても、従業員の異変を察知することができます。
最悪な状況になる前の早期発見にもつなげることが可能です。
導入企業様の口コミ
リモート業務の管理をする製品を導入するために20製品ほどを比較検討しました。選考ポイントは、2点あり、業務内容の把握とセキュリティ対策でした。この2点を実装している製品は少ないのですが、そのなかでクオリティの高さとコストの安さを兼ね備えているのがEye247でした。一般的にクオリティが高ければ、それに応じてコストも高くなるのが普通ですが、Eye247は見事にその両方を兼ね備えています。20製品ほどを調査しましたが、導入すべきはEye247しかないと絶対の自信がありました。 |
管理画面が軽量でサクサク動き、UIも比較的親切で分かりやすいです。 なにより、他社の類似製品と比較にならないほど安価なので 「まず試す」がしやすいのは大きなメリットだと思います。 安価でいて機能も必要十分なので、不満が少ない良い製品だと思います。 |
■まとめ:暑さ対策で従業員を守る
猛暑が常態化する中、暑すぎる職場環境は従業員の健康と業務効率に大きな影響を及ぼします。テレワークの導入によって、暑さから従業員を守るとともに、柔軟な働き方を実現することが重要です。今後の気候変動にも備え、企業として持続可能な働き方の構築を進めましょう。
この記事のポイント
|