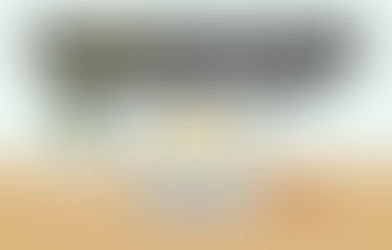営業のサボりやカラ出張をどう防ぐ?管理職が取るべき対応と最新ツール
- FuvaBrain
- 9月18日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年9月18日

営業職の「サボり」や「カラ出張」は、企業の生産性や信頼性を大きく損なうリスクがあります。実際、2022年に株式会社SATが行ったアンケート調査によると、営業職の86%がサボった経験があるというデータが報告されています。このような不正や非効率を放置すれば、組織全体の士気低下や優秀人材の離職、さらには企業のブランド毀損につながりかねません。
この記事では、その実態や原因、管理職が取るべき対応策を整理し、さらに最新ツールを活用した防止方法をご紹介します。営業現場の健全化や生産性向上を目指す方にとって、実践的なヒントとしてご活用ください。
※出典:株式会社SAT『営業パーソンのサボりに関するアンケート調査』
目次
営業のサボりとは?定義と具体例
営業がサボる主な原因一覧
「サボり癖」を生み出す構造的要因
事実の確認と証拠収集の重要性
注意や面談で心がけるポイント
根本原因の特定と業務・環境の改善
カラ出張の定義と具体的な手口
企業側に発生するリスク
従業員に及ぶリスク
制度面での防止策
システム面での防止策
成功事例
失敗事例
企業が今後取るべき検討ポイント
営業のサボり・カラ出張対策に『Eye“247” Work Smart Cloud』
サボりの早期発見が可能
スケジュール連携で空白の時間を検出
カラ出張の抑止・確認が可能
■営業のサボりの実態と背景
営業職は外回りや出張が多く、上司や同僚の目が届きにくい働き方をしています。そのため「サボり」や「カラ出張」といった行為が発生しやすい傾向があります。しかし、サボりが常態化すると組織の生産性や信頼性が損なわれ、重大な問題に発展するリスクがあります。そのため、営業によるサボりの実態や背景を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。
営業のサボりとは?定義と具体例
営業職における「サボり」とは、業務時間中に本来の業務を行わず私用に時間を費やす行為を指します。たとえば、外回り中に長時間カフェで過ごしたり、訪問先を装って自宅で休憩したりするケースなどです。こうした行為は、短期的には気付かれにくいものの、組織の信頼を損なうだけでなく、企業の売上やチームの士気低下に直結します。
営業がサボる主な原因一覧
理由 | 内容 | 組織に及ぶ影響 |
|---|---|---|
管理体制の不備 | 外回りや直行直帰で行動が見えにくい | サボり・カラ出張の温床になる |
過度なノルマ設定 | 高すぎる数字目標がストレスに | モチベーション低下、メンタル不調 |
業務の属人化 | 教育不足で負担が一部社員に集中 | 不公平感から不満や不正が増加 |
評価制度の不透明さ | 努力が正当に評価されない環境 | モチベーション低下や不公平感の蔓延 |
商材や会社への不信感 | 扱う商材に自信が持てない、会社方針に納得できない | モチベーション低下、離職リスク増大 |
職場文化の問題 | サボっても注意されない雰囲気 | 真面目な社員の士気が低下 |
「サボり癖」を生み出す構造的要因
営業のサボりが個人の資質だけでなく、組織の構造的な問題から生まれることも少なくありません。
たとえば、営業活動の管理が曖昧で、成果さえ出していればプロセスが問われない風土や、上司が現場の実態を把握できていない場合、サボり癖が定着しやすくなります。また、営業支援ツールや行動管理システムが未導入で、日報や報告が形骸化している場合も要注意です。
このような構造的要因を見直すことが、サボり防止のカギとなります。
1. 成果主義の歪み
結果だけを評価し、プロセスを軽視する管理体制では「見えない部分ならサボっても問題ない」という誤った意識が根づきやすくなります。プロセス評価制度を組み込み、営業の努力の過程を正しく評価できる仕組みを導入しましょう。
2. コミュニケーション不足
上司と部下の対話が乏しいと、業務上の悩みやストレスが放置され、営業のサボりやカラ出張といった形で表面化することがあります。定期的な1on1ミーティングやチーム会議を実施し、課題や不満を早期に共有・解決できる場を設けましょう。
3. 透明性の欠如
経費精算や行動記録の仕組みが曖昧な場合、不正が「やり得」となり、サボり癖が組織に広がっていきます。ITツールを導入し、勤務状況や出張経費のデータを活用することで、透明性の高い環境を整えましょう。
■「サボりがちな営業職」への対応策
営業のサボりやカラ出張が見受けられる社員に対しては、感情的に叱責するだけでは問題解決につながりません。管理職が取るべき対応は単なる叱責ではなく、事実の把握 → 原因分析 → 改善支援 → 再発防止の流れで対応することです。
以下で、具体的にどのようなアプローチが有効なのかを整理します。
事実の確認と証拠収集の重要性

営業職のサボりが疑われる場合、感情的な対応や憶測での指摘は逆効果となることが多いです。まずは冷静に事実確認を行い、客観的な証拠を収集することが重要です。GPSや営業支援ツールのログ、日報や経費精算書など、実際の行動履歴を確認しましょう。
証拠が曖昧なまま注意や処分を行うと、トラブルや不信感を招くリスクが高まります。事実に基づいた対応が、組織の信頼性を守るポイントです。
注意や面談で心がけるポイント
サボりが判明した場合、頭ごなしに叱責するのではなく、本人との面談を通じて状況や背景を丁寧にヒアリングしましょう。「なぜサボってしまったのか」「どんな課題や悩みがあるのか」を聞き出し、共感的な姿勢で接することが大切です。
また、改善のための具体的なアクションプランを一緒に考え、定期的なフォローアップを行うことで、再発防止につなげます。信頼関係を損なわずに指導することが、健全な組織づくりの第一歩です。
根本原因の特定と業務・環境の改善
営業のサボりの背景には、モチベーション低下や業務負荷の偏り、評価制度の不公平感など、さまざまな原因が潜んでいます。問題の解決には、単なる注意や監視だけでなく、業務プロセスや目標設定、評価制度の見直しなど、組織全体の環境改善が必要です。
また、営業支援ツールの導入や業務の見える化によって、サボりにくい仕組みを構築することも効果的です。根本原因を分析し、業務分担や教育体制を見直すことで再発防止につながります。
■カラ出張とは?企業と従業員に及ぼすリスク
カラ出張とは、実際には出張していないにもかかわらず、架空の旅費や宿泊費を経費として申請する不正行為を指します。営業によるサボりの一環として行われるケースも多く、企業のコスト増大やコンプライアンス違反といった深刻なリスクを招きます。
カラ出張の定義と具体的な手口
カラ出張は、実際には出張していないにもかかわらず、出張したと偽って経費を不正に請求する行為です。たとえば、私用の旅行を出張と偽装したり、架空の顧客訪問を申請したりするケースが挙げられます。このような不正は、企業のコスト増加や信頼性低下につながる重大な問題です。
手口 | 内容 | 企業側の損害 |
|---|---|---|
架空出張 | 実際には出張していないのに経費精算を提出 | 交通費・宿泊費の不正支出 |
出張目的の偽装 | 私用旅行を業務出張と偽る | 社内規程違反、発覚時の信頼失墜 |
経費の水増し | 実際より高額な交通手段や宿泊施設を利用 | コストの増大、経理部門の負担増 |
企業側に発生するリスク
カラ出張が行われた場合、企業にはさまざまなリスクが発生します。
まず、無駄な経費支出によるコスト増加が挙げられます。また、経費精算や出張管理の統制が甘いと、他の従業員にも不正が広がる恐れがあります。さらに、外部に不正が発覚した場合、企業の社会的信頼性が大きく損なわれ、取引先や顧客からの信用失墜につながることもあります。
これらのリスクを未然に防ぐためには、厳格な管理体制が不可欠です。
直接的な金銭的損失:不正経費の累積でコストが膨らみ、利益を圧迫します。
内部統制の形骸化:カラ出張が常態化すれば、内部統制が機能していないことを意味し、監査で問題視される可能性があります。
コンプライアンス違反による社会的信頼低下:「管理体制が甘い企業」として取引先・顧客からの信頼を失い、ブランド毀損につながります。
従業員に及ぶリスク
カラ出張を行った従業員は、懲戒処分や減給、最悪の場合は解雇といった厳しい処分が科されることがあります。また、社内での信頼を失い、キャリアに大きな傷がつくリスクもあります。さらに、同僚や上司との人間関係が悪化し、職場で孤立するケースも少なくありません。
一度不正が発覚すると、再起が難しくなるため、従業員にとっても大きなリスクとなります。
懲戒処分や解雇のリスク:就業規則違反として減給・出勤停止・解雇の対象となる場合がある
キャリアへの悪影響:不正履歴が社内外に知られると、昇進・転職に不利
人間関係の悪化:発覚すれば同僚や上司との信頼関係が崩壊し孤立する
■カラ出張の防止策・管理職が取るべき対応
制度面での防止策
カラ出張を防ぐためには、まず出張規程や経費精算ルールを明確に整備し、従業員に周知徹底することが重要です。そうすることでグレーゾーンをなくし、不正申請の抑制につながります。
また、出張申請や経費精算の際には、上司による承認フローを厳格に設けることで、不正の抑止力が高まります。上司の承認+経理部門の承認などダブルチェックを設けることで、カラ出張や水増し申請の発見につながります。
さらに、定期的な監査やチェック体制を導入し、規程違反がないかを確認することも効果的です。制度面の整備は、不正防止の基盤となります。
システム面での防止策
近年では、経費精算システムや営業支援ツール、GPS機能付きの業務アプリなど、テクノロジーを活用した不正防止策が普及しています。
経費精算システムでは、領収書の電子化や申請内容の自動チェックが可能です。データとして履歴を残しておくことで不正を発見しやすくなります。
また、営業支援ツールやGPSを活用することで、営業の行動履歴や訪問先をリアルタイムで把握でき、カラ出張やサボりなど、不正の早期発見につながります。
システム面の強化は、管理職の負担軽減にも効果的です。
■営業のサボり対策の事例
成功事例
ある企業では、営業のサボりやカラ出張の問題を受けて、出張規程の見直しと営業支援ツールの導入を同時に実施しました。
具体的には、出張申請や経費精算の承認フローを厳格化し、営業活動のスケジュールや訪問履歴をツールで可視化。これにより、サボりや不正の抑止効果が高まり、営業の行動が透明化されました。
結果として、営業活動の質が向上し、売上や顧客満足度も大きく改善しました。制度とツールの両輪で対策を進めることが、成果につながるポイントと言えます。
失敗事例
過度な監視や放置が逆効果を招いた事例も存在します。ある企業では、監視カメラによる過剰な行動管理を行った結果、営業のモチベーションが大きく低下し、離職者が増加したケースがあります。
また別の企業では、サボりを放置したことで、組織全体に不正が蔓延し、信頼性が損なわれました。
バランスの取れた管理と、現場の声を反映した制度設計が重要です。
企業が今後取るべき検討ポイント
1.制度面の見直し
出張旅費規程や勤怠ルールを明確にし、曖昧さをなくすことが重要です。さらに、現場の声を反映し、実態に即した制度設計を行うことが求められます。
2.ツールの活用
Eye“247” Work Smart Cloud のような行動ログ・勤怠乖離チェック機能を備えたツールを導入し、営業のサボりやカラ出張を“見える化”します。最新テクノロジーを積極的に取り入れる姿勢が、効果的な対策につながります。
3.文化づくり
「監視されているから守る」のではなく、「透明性が高いから不正は起きにくい」という文化を浸透させることが大切です。モチベーション向上施策と組み合わせて推進することで、健全な組織風土を醸成できます。
■営業のサボり・カラ出張対策に『Eye“247” Work Smart Cloud』
営業のサボりやカラ出張は、従来の目視チェックや紙ベースの経費精算だけでは防止が難しく、管理職や人事部門の大きな悩みとなっています。こうした課題を解決するのが、業務ログを自動収集し「見える化」を実現するクラウドサービス『Eye“247” Work Smart Cloud』です。
サボりの早期発見が可能
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、PC操作ログにより社員一人ひとりの実際の働き方を可視化します。「誰が・いつ・どの程度・どんな作業をしたか」が分かるようになっており、業務内容や業務集中度のログからサボりを検出することができます。
これにより、テレワークや出張先など、管理者から見えない状態であっても、サボりの早期発見が可能です。
スケジュール連携で空白の時間を検出
カレンダーツールから自動でスケジュールを読み込み、内容を表示することができます。それにより、カレンダーツールに営業の予定を入れれば、予定がある時間と実際の実働時間を突合し乖離を見つけることが可能です。
PC操作ログもなく、営業予定もない空白の時間があれば、サボりがひと目で分かります。
カラ出張の抑止・確認が可能
『Eye“247” Work Smart Cloud』の勤怠管理オプションでは、iPhoneのGPS機能を使い、勤務中の行動(移動)履歴を地図上にマッピングして表示します。
位置情報の記録により、カラ出張であっても不審な動きからサボりを検知することが可能です。
■まとめ:健全な営業組織をつくるために
営業のサボりやカラ出張は、個人の怠慢ではなく組織全体の課題としてとらえる必要があります。
制度やツールの導入、現場の声を反映した柔軟な運用、そして最新のテクノロジーの活用によって、これらの問題は十分に防止・改善が可能です。管理職は、単なる監視や処罰にとどまらず、営業のモチベーション向上や健全な組織風土の醸成にも注力しましょう。
その実現を後押しするのが『Eye“247” Work Smart Cloud』です。健全で透明性の高い営業組織を構築するために、最新ツールの活用を積極的に検討することをおすすめします。
この記事のポイント
|