【企業向け】退職者による顧客情報持ち出しは罪?法律・事例・対策も解説!
- 2025年6月26日
- 読了時間: 13分
更新日:2025年7月22日
更新日:2025年7月22日
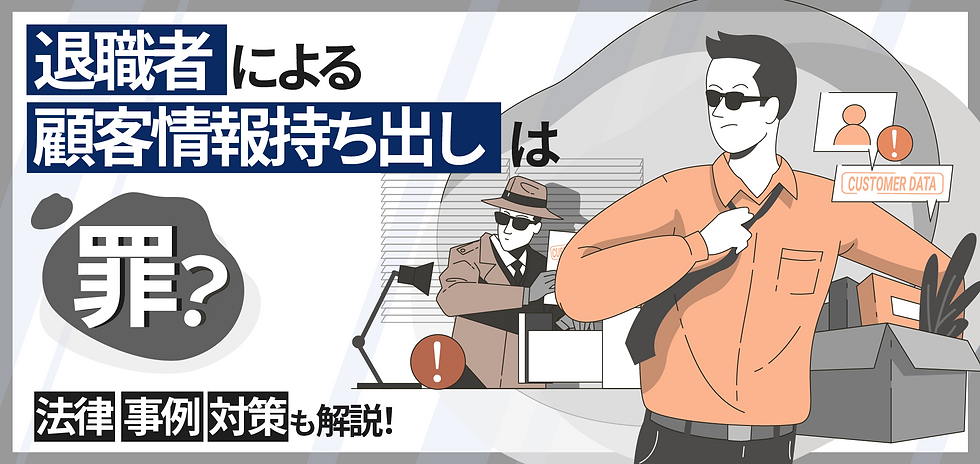
退職者による顧客情報の持ち出しは、企業にとって重大なリスクです。転職先での情報流用、顧客との信頼関係の崩壊、法的トラブルなど、その影響は計り知れません。
この記事では、なぜこの問題が増えているのか、実際の事例や法的な位置づけ、企業がとるべき対策までを網羅的に解説します。
目次
競争激化と転職事情の変化
個人利用デバイスの増加(BYOD)
クラウド・共有ツールの浸透
退職後の競合企業への情報流出
USBや私用クラウドを経由した情報漏洩
社内信頼の低下と風評被害
不正競争防止法違反とは
個人情報保護法違反の可能性
刑事告訴・民事訴訟の対象となるケース
退職者の顧客情報持ち出しを事前に防ぐために企業が取るべき対策
予防策としての雇用契約・誓約書の役割
退職時の端末・クラウド・メディアの確認項目
運用ルールで「持ち出させない仕組み」を作る
PC操作ログ・USB使用履歴のチェック方法
社内教育とツールによる継続的な防止策
情報の持ち出しを検知する
情報持ち出しの抑制になる
■退職者による情報漏洩が増えている実態
独立行政法人・情報処理推進機構(IPA)では、2020年10月に企業の情報漏洩の実態や対策、取り組み状況などを調査しました。その結果、情報漏洩ルートに関して「誤作動・誤認」での情報漏洩が減少する一方で「中途退職者」による情報漏洩は36.3%と前年度よりも7.7%増と、内部不正による情報漏洩割合は増加傾向にあることが分かりました。
人材の流動化やインターネット技術の進化、テレワークの普及のなどさまざまな背景が推測されますが、いずれにせよ退職者に情報の持ち出し・漏洩に対する対策が必須になっています。
※出典:IPA「企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」
■なぜ退職者による情報持ち出しが増えているのか
近年、退職者による顧客情報の持ち出しが増加しています。その背景には、テクノロジーの進化によりデータの携帯・転送が容易になったこと、働き方の多様化による管理の難しさ、そして業界間の競争激化など、複数の要因が関係しています。
ここでは、情報漏洩リスクが高まる要因を3つに分けて解説します。
競争激化と転職事情の変化
近年、業界間の競争が激しさを増し、それに伴い転職市場も活性化しています。従業員がキャリアアップや待遇改善を理由に同業他社へ転職する事例が増加する中、自分のスキルや実績をアピールする手段として、在籍中に得た顧客情報を無断で持ち出すリスクが高まっています。
その際、自分の実績を示す目的や次の業務の準備として顧客情報を持ち出す事例が見られます。
人材の流動性に関する記事:人材流出が止まらない原因をデータで解明し、定着率を高める方法5選
個人利用デバイスの増加(BYOD)
BYOD(Bring Your Own Device)とは、従業員が個人所有のスマートフォンやノートパソコンなどを業務に使用する形態を指します。このBYODの普及により、私物スマホやPCから業務データにアクセスできる環境が整ったことで、企業が業務データへのアクセスや保存先を完全に管理することが難しくなっています。たとえば、私物スマートフォンから社内のファイルサーバーにアクセスし、ファイルをクラウドストレージに保存するなど、外部への情報流出が発生しやすい環境が生まれています。
シャドーITに関する記事:シャドーITの5大リスクとは?企業がとるべき対策方法
クラウド・共有ツールの浸透
Google Drive、Dropbox、Slack、Chatworkなどのクラウド共有ツールが業務に浸透することで、情報の利便性は向上した一方、管理者の目が届かない場所でのデータ持ち出しが容易になりました。特に、アクセス権限やログ管理が不十分な状態では、意図的な不正持ち出しだけでなく、無意識のうちにファイルを個人のクラウドにコピーしてしまうリスクも存在します。
テレワークの増加
テレワークの普及により、自宅や外出先から社内システムにアクセスする機会が増えました。これにより、従来は物理的に制限されていた情報持ち出しのハードルが大幅に下がっています。自宅ネットワークのセキュリティが社内より甘いケースも多く、社内での目が届きにくいため、不正なファイル転送や外部ストレージ利用なども発見が遅れやすいです。そのため、顧客情報など情報の持ち出しがしやすくなっており、情報漏洩のリスクを助長しています。
テレワークに関する記事:テレワーク時代の情報漏洩対策5選!中小企業の情報漏洩リスクを最小限に抑える運用体制とは
■退職者の顧客情報持ち出しによる問題点

退職者による顧客情報の持ち出しは、企業にとって重大な経営リスクとなります。たとえば、競合企業に顧客リストが渡れば、顧客がそちらに流れてしまい、売上の大幅な減少につながる恐れがあります。また、持ち出された情報が個人情報や営業秘密であった場合、漏洩先の企業や当局との法的トラブルに発展することもあります。
さらに、情報が外部に流出した事実が取引先や顧客に知られた場合、企業の機密管理体制が甘いと評価され、信用失墜や風評被害にもつながります。加えて、内部統制の不備が露呈すれば、既存の従業員の士気低下や、優秀な人材の流出を招く結果にもなりかねません。
■実際に起きた顧客情報持ち出し事例と企業への影響
顧客情報の不正持ち出しは、現実に数多くの企業で発生しており、その影響は経済的損失にとどまらず、企業の信用失墜にもつながります。 実際に報告された代表的な事例を紹介し、どのような手口で情報が持ち出され、どのような被害が生じたのかを解説します。
退職後の競合企業への情報流出
あるIT企業では、営業担当の元社員が顧客リストや過去の商談履歴を無断で持ち出し、転職先である同業他社で営業活動に使用しました。結果として、旧所属企業は複数の主要顧客を失い、年間数千万円規模の売上損失が発生。企業は損害賠償を求めて民事訴訟を提起し、法廷での争いに発展しました。
USBや私用クラウドを経由した情報漏洩
製造業の企業では、退職直前の従業員が社内の設計図面や顧客別の納品仕様書をUSBメモリに保存して持ち出し、その後、個人のクラウドストレージにアップロードしていたことが判明。元社員が情報を別会社に提供していたことで、取引先からの信用が低下し、一部取引停止に至りました。
USBからの情報漏洩に関する記事:USB外部記憶装置の情報漏えいを防ぐために、効果的なセキュリティ対策とは?
社内信頼の低下と風評被害
情報セキュリティの甘さがSNSや業界内に広まり、「あの会社は情報が漏れる危険がある」との評判が立った事例があります。実際、採用活動にも影響が出ており、内定辞退者が増えたほか、一部の既存取引先が別の企業への切り替えを検討する事態となりました。
■顧客情報を持ち出す行為はどんな罪に問われるのか
無断で退職者が顧客情報を持ち出す行為は、複数の法令違反に問われる可能性があります。
主に問われる可能性がある罪としては
不正競争防止法違反:営業秘密(顧客リスト等)の不正取得・使用・開示に対する刑事罰・民事賠償。
個人情報保護法違反:本人の同意なく顧客の個人情報を外部へ持ち出した場合の行政処分や罰金。
業務上横領罪(刑法253条):業務で知り得た情報を私的に流用・持ち出す行為が該当するケースもあり。
信用毀損罪・名誉毀損罪:顧客情報の漏洩が企業や顧客の社会的評価を害する場合。
民事上の損害賠償責任:企業からの損害賠償請求の対象となる(債務不履行・不法行為)。
があげられます。
また、顧客情報等、業務上知り得た情報を無断で社外に持ち出す行為は法律に抵触する可能性があることを、従業員へ周知することも内部不正による情報漏洩対策として有効です。
不正競争防止法違反とは
営業秘密を不正に持ち出した場合、不正競争防止法により刑事罰や損害賠償請求の対象になります。
不正競争防止法は、企業の営業秘密を守るための法律です。顧客リストや価格表、提案資料などが営業秘密として認定されると、それを不正に取得・使用・開示した場合、10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金、あるいはその両方という重い刑事罰が科されます。また、企業は加害者に対して損害賠償請求を行うことも可能です。
個人情報保護法違反の可能性
顧客の個人情報を無断で持ち出した場合、個人情報保護法違反となり、行政指導や罰金が科される可能性があります。
個人情報保護法は、顧客の氏名・住所・連絡先などの個人情報を守るための法律です。顧客の同意なくその情報を社外に持ち出した場合、個人には1年以下の懲役または100万以下の罰金。法人の場合は、最大で1億円以下の罰金や、命令違反時には刑事罰が科されることがあります。情報漏洩が発覚すれば、個人情報保護委員会からの指導や企業名の公表といった社会的制裁も伴います。
刑事告訴・民事訴訟の対象となるケース
顧客情報の持ち出しが悪質と判断された場合、企業は刑事告訴や民事訴訟を通じて元社員に法的責任を問うことが可能です。 たとえば、意図的にUSBなどにデータを保存し転職先に提供した場合などは、業務上横領や窃盗に類する行為と見なされ、逮捕・起訴されるケースもあります。さらに、民事訴訟では、持ち出しによって失われた売上や信用の損害を元社員に請求することが可能です。
■情報の持ち出しに気づいたときの企業対応フロー
情報の持ち出しが発覚した際、迅速かつ適切な対応が求められます。対応を誤ると、さらなる情報流出や訴訟リスクにつながる可能性もあります。以下のフローに従って、冷静に状況を把握し、必要な対応を進めましょう。
状況の把握と証拠の確保:まずは、どの情報が、どのような手段で、誰によって持ち出されたのかを把握し、操作ログや通信記録などの証拠を保全します。
社内関係者への共有と初動対応:人事・法務・情報システム部門と連携し、緊急の対策を講じます。対象社員のアクセス権限を速やかに停止することも重要です。
関係者へのヒアリングと状況確認:本人への聞き取りを実施し、故意・過失の有無や経緯を確認します。
外部専門家や顧問弁護士への相談:持ち出された情報が営業秘密や個人情報に該当するかどうかを判断し、必要に応じて法的措置を検討します。
被害の最小化と再発防止策の実施:被害を最小限に食い止めるため、影響を受ける顧客への連絡や社内体制の見直しを行います。
社外発表の内容決定:情報漏洩があった際、影響の範囲の特定や関係各所との連携が取れたタイミングで、発表方法や内容を選定し社外に向けて発信します。
■退職者の顧客情報持ち出しを事前に防ぐために企業が取るべき対策
退職意向が出た段階から、情報漏洩を未然に防ぐための対策が必要です。とくに、アクセス権限の見直し、社内規定の周知徹底、デバイスやアカウントの確認を早期に行うことで、顧客情報の不正な持ち出しを防ぐことができます。
予防策としての雇用契約・誓約書の役割
入社時や退職時に、顧客情報の取り扱いに関する誓約書を取り交わすことで、情報漏洩に対する抑止力を高めると同時に、違反時の法的根拠が明確になります。とくに、退職後の情報利用を禁じる文言や秘密保持義務の継続性を明記することで、後のトラブルを未然に防ぐ効果があります。
退職時の端末・クラウド・メディアの確認項目
退職時には、業務端末の返却確認を漏れなく実施します。
業務用PCやスマートフォンの返却だけでなく、クラウドアカウント(Google Workspace、Microsoft 365等)のアクセス権停止、USBや外付けハードディスク、社内サーバとの同期フォルダの確認を徹底することが必要です。また、デバイス内に残されたデータを完全に消去することも重要です。
運用ルールで「持ち出させない仕組み」を作る
ファイルの暗号化や印刷・外部出力の制限など、物理的な持ち出しを防ぐ設定を実施します。 業務データを外部デバイスにコピーできないようUSBポートを制限する、社外ネットワークへのアップロードを制御する、印刷制限や自動暗号化の導入など、システム面での制御を強化することで、物理的なデータ持ち出しを防止できます。加えて、これらのルールを社員に周知し、遵守を徹底する仕組みが不可欠です。
PC操作ログ・USB使用履歴のチェック方法
従業員が業務端末でどのようなファイル操作を行っているかをPC操作ログとして記録し、特に退職意向が示された段階で、USB使用状況やファイル転送履歴を重点的にチェックします。過去の操作履歴を可視化することで、不審な行動の兆候を早期に察知し、証拠としても活用できます。
社内教育とツールによる継続的な防止策
情報漏洩対策の効果を持続させるには、定期的なセキュリティ研修の実施が重要です。併せて、PC操作ログやアクセス監視ツールを導入・活用することで、従業員の行動を常に見える化し、不正をしにくい環境を作ることができます。教育とツールの両輪で、意識と行動の両面から対策を行いましょう。
■PC操作ログや監視ツールによる事前検知のすすめ
退職者による情報の不正持ち出しは、事後対応では手遅れになるケースもあります。そこで重要なのが、日常的に社内システムの利用状況を可視化し、不審な動きを早期に検知できる体制づくりです。
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、PC操作ログや外部デバイスの使用履歴、個人情報の保持状況などをリアルタイムに監視できるクラウド型の統合ツールです。ここでは、『Eye“247” Work Smart Cloud』の機能をいくつかご紹介します。
情報の持ち出しを検知する
『Eye“247” Work Smart Cloud』では、情報漏洩リスクがある状態を事前に個人情報保持チェックなどで把握し、情報漏洩に繋がりそうな行動(深夜の操作、ファイル操作、USB操作、印刷履歴、禁止ソフトの起動など)を記録することで、持ち出しがあった際の証拠を残します。
これらのデータを日常的に監視・分析することで、情報の持ち出しの兆候を早期に察知することが可能になります。
情報持ち出しの抑制になる
また、様々なログを記録していることを従業員に伝えることで情報漏洩の抑止につなげることができます。
不正が発生する要因には、「動機」、「機会」、「正当化」の3つの要素(不正のトライアングル)があると言われており、不正を行う動機、不正ができる機会、不正を正当化できる理由、この3つが揃った時に不正が発生します。
『Eye“247” Work Smart Cloud』で様々なログを記録している事実を従業員が知ることで、不正の「機会」を減らし、情報持ち出しの抑制をすることができます。
■まとめ:退職者リスクを想定した事前対策が企業を守る
退職者による顧客情報持ち出しは、企業の信頼や業績に甚大な影響を与えかねません。技術の進展や働き方の変化によりリスクが高まるなか、企業は「起きてから対応」ではなく、「起こさせない体制づくり」が求められています。雇用契約や誓約書による法的対応だけでなく、ログ監視や行動の可視化、教育を通じた意識づけなどの多層的な対策を講じることで、リスクを未然に防ぎましょう。
退職者リスクは、すべての企業にとって避けて通れない課題です。今こそ、対策を仕組み化し、組織全体で情報資産を守る意識を高めていくことが重要です。
この記事のポイント
|














