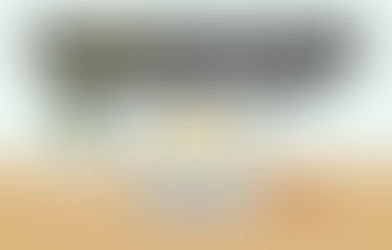台風時の出勤命令にNO!会社のルールと従業員が守るべき権利
- FuvaBrain
- 9月8日
- 読了時間: 10分
更新日:2025年9月8日

台風などの自然災害が接近するとき、従業員に「出勤しなさい」と命じる企業は少なくありません。
しかし、「台風出勤」を強制することは従業員の安全を脅かすだけでなく、企業の社会的評価や法的リスクにも直結します。
この記事では、台風時の出勤命令をめぐる法的枠組み・従業員の権利・企業がとるべき対応を解説します。さらに、台風時の業務継続を支える最新クラウドツールもご紹介します。安全と業務を両立するためのヒントにお役立てください。
目次
台風時の出勤経験がある人が多い
台風出勤が問題視される理由と社会背景の解説
台風接近時の出勤命令に対する従業員の本音とは
台風出勤のトラブル事例
台風出勤に関する明確な法律は存在しない
企業に課せられる安全配慮義務
強制出勤・パワハラ行為と違法性の判断基準
従業員が持つ主な権利
自己判断のポイント
従業員にありがちな誤解
安全確保のための対応策
業務継続のための柔軟な働き方
BCPの推奨例
■台風で出勤を命じる会社はおかしいのか?
台風の接近時に出勤を命じる会社に対して「おかしいのでは?」と疑問を持つ人が増えています。実際、台風による強風や大雨で交通機関が止まったり、道路が冠水したりと、通勤途中の事故リスクが高まる中、無理に出勤を強制することは従業員の安全を軽視していると受け取られがちです。
一方で、業種や業務内容によっては出勤が必要な場合もあり、会社側も判断に迷うケースが多いのが実情です。社会全体で「安全第一」の意識が高まる中、台風時の出勤命令の是非が問われています。
台風時の出勤経験がある人が多い
アスクル株式会社は、2022年に台風出勤についての調査を実施しました。その結果、台風による交通機関影響発生時の出勤経験「あり」は、57.2%、首都圏への出勤者は7割以上が「あり」と回答しました。
多くの人が危険を認識していても、台風接近時の職場のルールや方針が決まっていないことから出勤せざるを得ない状況になっています。

※出典:アスクル株式会社『「職場の防災への意識や準備・対策」に関する実態調査<後編:台風>』
台風出勤が問題視される理由と社会背景の解説
台風出勤が問題視される最大の理由は、従業員の命や健康を守るべき企業の責任が問われるからです。
近年、自然災害による被害が増加し、従業員の安全配慮義務が社会的にも強く求められるようになりました。
また、SNSやニュースで「台風でも出勤を強制された」という声が拡散され、企業イメージの低下や炎上リスクも高まっています。働き方改革やテレワークの普及もあり、従来の「何があっても出勤」という価値観が見直されるようになってきました。
台風接近時の出勤命令に対する従業員の本音とは
台風接近時に出勤を命じられた従業員の多くは、不安や不満を感じています。
「自分や家族の安全が心配」「交通機関が止まったらどうしよう」「会社は本当に従業員を大切にしているのか?」といった声が多く聞かれます。
一方で、「自分だけ休むことにためらいを感じる」「評価が下がるのでは」といったプレッシャーを感じる人も少なくありません。従業員の本音を無視した出勤命令は、モチベーション低下や離職リスクにもつながるため、企業側も慎重な対応が求められます。
台風出勤のトラブル事例
SNSで炎上した企業の例
ある企業では、台風で交通機関が全面運休したにもかかわらず出勤命令を出し、従業員がSNSに投稿したことで大きな炎上につながりました。企業名は瞬く間に拡散され、ブランドイメージが失墜しました。
法的トラブルに発展したケース
過去には、台風出勤を強いられた従業員が通勤中に事故に遭い、労災認定が争点となった事例もあります。裁判では「安全配慮義務違反」が問われ、企業側が責任を負う結果となりました。
■台風時の法的な枠組みと義務
台風出勤に関する明確な法律は存在しない
台風や大雨などの自然災害時に出勤を命じることについて、直接的に規定した法律はありません。そのため、出勤の可否は会社の就業規則や判断に委ねられるケースが多いです。
ただし、会社都合で休業を命じた場合は休業手当の支払い義務が発生するなど、労働基準法上のルールは適用されます。従業員が自己判断で欠勤した場合、原則として賃金は支払われませんが、会社の判断や状況によって対応が異なるため注意が必要です。
企業に課せられる安全配慮義務
労働契約法第5条では、企業(使用者)は従業員の生命や健康を守る「安全配慮義務」を負っています。台風などの災害時に無理な出勤を命じ、従業員が事故やケガをした場合、企業は安全配慮義務違反として責任を問われる可能性があります。台風の中で出勤させる場合、以下のようなリスクが発生します。
強風・冠水による通勤中の事故
公共交通機関の運休や遅延による帰宅困難
災害時に従業員が会社に閉じ込められるリスク
これらを無視して「台風出勤させる会社」となれば、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
暴風雨や交通機関のマヒが予測される場合は、出勤を強制しない・在宅勤務を推奨するなどの配慮が求められ、企業は従業員の安全を最優先に考えた判断が必要です。
強制出勤・パワハラ行為と違法性の判断基準
台風時に「出勤しないと評価を下げる」「欠勤は認めない」など、強制的な出勤命令やパワハラ的な言動は違法と判断される場合があります。特に、従業員の安全が確保できない状況での強制出勤は、安全配慮義務違反や労災認定のリスクも高まります。
企業は、従業員の状況や交通機関の運行状況を十分に考慮し、無理な命令や圧力をかけないことが重要です。従業員も、不当な強制やパワハラを受けた場合は、労働基準監督署などに相談することができます。
■従業員が守るべき権利と自己判断のポイント
台風時の出勤命令に対して、従業員が自分の身を守るために知っておくべき権利や、自己判断のポイントがあります。
会社の指示に従うことが原則ですが、命や健康に危険が及ぶ場合は、無理に出勤しない選択も重要です。また、会社の就業規則や災害時のガイドラインを事前に確認し、どのような場合に欠勤や在宅勤務が認められるのかを把握しておくことが大切です。
自分の判断だけでなく、会社としっかりコミュニケーションを取ることもトラブル回避のポイントです。
従業員が持つ主な権利
権利 | 内容 |
|---|---|
有給休暇 | 台風を理由に取得可能 |
安全を守る権利 | 危険がある場合は出勤拒否が正当化される可能性あり |
労災認定 | 通勤中の事故は「通勤災害」として労災の対象 |
記録保持 | 出勤命令や上司の指示を証拠として残すことが可能 |
自己判断のポイント
会社が「自己判断に任せる」とするケースもあります。このときは以下を基準にしましょう。
交通機関の状況:電車やバスが運休している場合は無理に出勤しない。
自治体からの警報や避難指示:特別警報や避難指示が出ている場合は安全を最優先に。
会社の就業規則やマニュアル:台風出勤に関する明記があるか確認する。
従業員にありがちな誤解
「会社が出勤を命じたら絶対に従わなければならない」「自己判断で休むと必ず給料が減る」といった誤解を持つ従業員も多いです。
実際には、会社にも安全配慮義務があり、危険な状況下での無理な出勤命令は違法となる場合があります。また、会社都合で休業となった場合は休業手当が支払われるケースもあるため、正しい知識を持つことが大切です。
不明点があれば、会社や労働基準監督署に相談しましょう。
■企業側の対応策〜安全確保・業務継続・BCPの推奨例〜
企業は台風などの自然災害時に、従業員の安全を守りつつ業務を継続するための対応策を講じる必要があります。安全確保のためのガイドライン策定や、テレワーク・時差出勤の導入、BCP(事業継続計画)の整備などが重要です。
従業員の命と健康を最優先に考え、柔軟な働き方を推進することで、企業リスクの低減と従業員満足度の向上が期待できます。
安全確保のための対応策
企業は、台風接近時に従業員の安全を守るため、出勤の可否や在宅勤務の推奨、交通機関の運行状況に応じた柔軟な対応を行うことが求められます。また、災害時の連絡体制や緊急時のマニュアルを整備し、従業員が安心して働ける環境を作ることが重要です。
公共交通機関が運休した場合は出勤を免除
警報や避難指示の段階で自宅待機を指示
災害時専用の社内連絡チャネル(メール・チャット)を設け、情報を即時共有
など、従業員の安全確保を最優先にした判断が、トラブル防止や企業の信頼性向上にもつながります。
業務継続のための柔軟な働き方
出勤が困難な状況でも業務を止めないためには、柔軟な勤務体制が欠かせません。
対応策 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
在宅勤務(テレワーク) | 業務をオンラインで継続 | 出勤リスクゼロで安全確保 |
時差出勤 | 台風のピーク時間を避けて通勤 | 交通混雑や事故リスクを低減 |
振替勤務 | 台風当日を休業扱いにし、別日で勤務 | 生産性を確保しつつ従業員を守れる |
BCPの推奨例
BCP(事業継続計画)は、災害時にも事業を継続できるようにするための計画です。台風などの自然災害に備え、事前に業務の優先順位や代替手段、緊急時の連絡体制を明確にしておくことが重要です。
BCPを策定・実践することで、従業員の安全確保と企業の信頼性向上につながります。
出勤基準を数値化:(例)風速◯m以上、特別警報発令時は全社員在宅勤務へ切り替え。
ITツールを活用:クラウド型勤怠管理・業務可視化ツールを導入し、自宅からも業務を確認できる体制に。
事前訓練の実施:台風シーズン前に在宅勤務シミュレーションを行い、通信環境や業務連携に問題がないか検証。
■『Eye“247” Work Smart Cloud』の導入で、柔軟な出勤対応と安全確保を両立

台風の接近時に「出勤せよ」と命じる会社は、従業員から「安全より業務を優先している」と見られがちです。しかし、業務を止めずに従業員の安全も確保する方法があります。
その鍵となるのが、クラウド型業務可視化ツール 『Eye“247” Work Smart Cloud』 です。
Eye“247” Work Smart Cloud が解決できること
課題 | 解決策 | メリット |
|---|---|---|
出勤しないと業務状況が見えない | PC操作ログ・稼働状況を自動取得 | 管理職が在宅勤務でも業務進捗を把握 |
勤怠管理が曖昧になる | 勤怠乖離チェック機能で勤務実態を正確に記録 | 出退勤のトラブルを防止 |
生産性が下がる懸念 | ダッシュボードで部署・個人単位の業務を可視化 | 出勤せずともチームの進捗を共有可能 |
情報漏えいリスク | USB利用ログやアクセスログを自動記録 | 災害時のセキュリティ事故も抑制 |
Eye“247” Work Smart Cloud の導入で台風時に得られる効果
「台風時に出勤させる会社」と批判されないためには、テレワークや在宅勤務を安全に運用できる環境づくりが欠かせません。
『Eye“247” Work Smart Cloud』を導入すると、以下の3つの効果が主に得られます。
台風時でも「在宅勤務=業務停止」にならず、安全確保と事業継続を両立
出社組・在宅組を混在させても、同一の基準で勤務実態を可視化
勤怠と業務ログが自動で残るため、労務リスクの回避にもつながる
結果として、企業は安全確保と業務継続を両立でき、従業員も安心して働ける環境を手に入れられます。
■まとめ:台風時の出勤命令と従業員の正しい対応・企業の今後の役割
台風時の出勤命令は、従業員の安全と企業の業務継続のバランスが問われる重要なテーマです。
法律上、明確な規定はありませんが、企業には安全配慮義務があり、従業員も自分の命と健康を守る権利があります。
台風は毎年繰り返し訪れる自然災害です。「従業員を守る企業」こそが、信頼される企業として選ばれる時代になってきています。
この記事のポイント
|