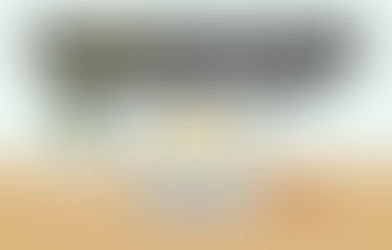窓際社員(窓際族)の特徴と実態。解雇の可否や企業の対応策とは?
- FuvaBrain
- 9月26日
- 読了時間: 14分
更新日:2025年9月26日

企業に在籍していながら活躍の場を失い、組織の片隅に追いやられる「窓際社員(窓際族)」。かつては一部の中高年層に限られた現象とされていましたが、現在では若手社員にも広がりつつあります。
この記事では、窓際社員の定義や特徴、企業にもたらすリスク、解雇の可否といった法的観点、さらに効果的な対処法を詳しく解説します。管理職や人事担当者にとって避けて通れないこの課題に、どのように向き合えばよいのかを考えていきましょう。
目次
「閑職」「余剰人員」「社内ニート」との違い
窓際社員になりやすい人の特徴
なぜ「窓際社員」が生まれるのか?
若手にも広がる「新しい窓際族」とは
無駄な人件費と生産性の低下
組織のモラル低下と離職率の上昇
情報漏洩・内部不正リスク
窓際社員を「クビにできない」と言われる理由
解雇が認められるケース・認められないケース
解雇以外の選択肢を提示するのが現実的
主な対応策一覧
対応ステップ
データに基づく客観的マネジメントの重要性
窓際社員へのマネジメントにも最適な『Eye“247” Work Smart Cloud』
窓際社員の早期発見に役立つログ管理
配置転換や再活用の判断材料としてのデータ活用
客観的な数値で公平な人事評価を実現
■ 窓際社員(窓際族)とは何か
「窓際社員(窓際族)」とは、企業内で出世コースから外れ、会社に在籍しているものの、重要な仕事や役割を与えられず、組織の中で存在感が薄くなってしまった社員を指します。
「窓際」という言葉は、オフィスの隅や窓際に追いやられ、実質的に仕事がない、または軽視されている状態を象徴する表現で、高度経済成長期の日本企業文化に由来します。
一見すると人材不足の現代では無縁のように見えますが、実際には20~30代の若手層に「窓際化」が見られるようになっています。
この状態は本人のモチベーション低下だけでなく、企業全体の生産性低下や人件費の無駄にもつながるため、管理職や人事担当者にとって重要なテーマです。
「閑職」「余剰人員」「社内ニート」との違い
「窓際社員」と似た言葉に「閑職」「余剰人員」「社内ニート」などがありますが、それぞれ意味やニュアンスが異なります。
用語 | 特徴 | 主な違いのポイント |
|---|---|---|
窓際社員(窓際族) | 在籍しているが責任ある仕事を与えられない。評価や配置転換でキャリアが停滞。 | 組織内で「存在するが活用されない」状態 |
閑職 | 役職名は残っているものの、実質的な権限や業務を持たないポジション。 | 形式的な役職のみが残っている状態 |
余剰人員 | 事業縮小や再編でポストがなくなり、配置転換を待つ人材。 | 経営判断による人員過多の影響が大きい |
社内ニート | 在籍しているが実務が与えられず、時間を持て余している状態。 | 本人の意思やスキル不足が要因の場合も多い |
窓際社員はこれらの要素を一部含みながらも、「組織に属しているが活用されない」というニュアンスが強いのが特徴です。
■ 窓際社員の特徴と生まれる要因
窓際社員になりやすい人の特徴
窓際社員は「やる気がない人」だけを指すわけではなく、組織と本人の双方に要因があるケースが多いです。以下の表に、窓際社員の典型的な特徴を整理しました。
特徴カテゴリ | 具体例 | 企業側から見える姿 |
|---|---|---|
業務面 | ・重要な仕事やプロジェクトを任されない ・単純作業や補助的業務ばかりを担当 | 成果が見えにくく、評価しづらい |
モチベーション | ・変化や新しいことに消極的 ・積極的に発言しない ・新しいことを学ぼうとしない | チーム全体に無気力感を広げるリスク |
スキル/能力 | ・業務スキルが時代に合わなくなっている ・ITツールや新制度に適応できない ・スキルのアップデートを怠る | 若手との差が広がり、戦力化が難しい |
人間関係 | ・コミュニケーションが苦手 ・上司や同僚とのコミュニケーション不足 ・孤立気味で相談相手がいない | チーム連携の阻害要因になる可能性がある |
環境 | ・年功序列や終身雇用が根強い | 年齢や勤続年数だけでポジションが維持されるため、本人が努力不足に陥る |
なぜ「窓際社員」が生まれるのか?
窓際社員(窓際族)は、本人の努力不足だけでなく 組織の制度や環境とのミスマッチ によって生まれます。ここでは、主な理由を「個人要因」「組織要因」の2つに分けて整理します。
個人要因によるもの
新しい業務や技術に対応できずスキル不足に陥ること、キャリアの将来像を描けずモチベーションを失うこと、積極的に発言や提案をせず受け身に徹してしまう姿勢などが、窓際社員を生む個人要因になります。これらは本人の意識や努力に関わる部分が大きく、適切なサポートや教育で改善できる可能性があります。
スキル不足:新しいITツールや業務フローに適応できない
モチベーション低下:目標やキャリアビジョンが描けず意欲を失う
消極的な姿勢:発言や提案を避け、受け身に徹する傾向が強い
組織要因によるもの
年功序列や終身雇用が根強い企業では、能力や成果に関係なく在籍し続ける社員が増え、結果的に窓際社員が生まれやすくなります。また、適性を無視した配置転換が行われると能力を十分に発揮できず、評価制度が曖昧だと努力や成果が正しく反映されずに不満や無力感を抱くようになります。
このような状況を放置すると、企業全体の生産性や士気の低下につながるため、早期の対応が求められます。
年功序列や硬直的な人事制度:年齢や勤続年数で昇進が決まり、役割を失った中高年が生まれる
配置転換の失敗:スキルや適性を無視した異動で能力を発揮できない
評価制度の曖昧さ:成果や努力が正しく反映されず、社員が不満や無力感を抱く
若手にも広がる「新しい窓際族」とは
かつては中高年層に多いとされた窓際社員ですが、近年では20代〜30代の若手層でも「窓際化」が見られるようになっています。
「新しい窓際族」が増えた背景には、ワークライフバランスを重視してあえて出世を望まない若者が増加していることや、人材不足によるスキルのミスマッチが増えていることが挙げられます。
さらに、テレワーク環境では働く姿が見えにくく、成果が曖昧な社員が「窓際扱い」されやすいといった課題も発生しています。これらは管理職・人事が早期に把握し、支援するべき組織課題であり、データによる業務実態の把握が不可欠です。
■ 企業への悪影響とリスク

無駄な人件費と生産性の低下
窓際社員を放置すれば、企業は本来必要のない人件費を支払い続けることになります。このコストは、直接的な利益を生み出さないため、経営資源の無駄遣いとなります。
また、他の社員のモチベーションや生産性にも悪影響が及び、組織全体のパフォーマンスが低下します。特に年功序列型の企業では、役職や給与が高いまま業務量が少ない社員が増えやすく、経営効率の悪化にもつながります。
このような状況を改善するためには、適切な人員配置や業務の見直しが必要です。
組織のモラル低下と離職率の上昇
窓際社員の存在は、組織のモラルや職場環境にも悪影響を及ぼします。
「働かなくても給料がもらえる」という姿勢が広がると、周囲の社員の士気が低下し、「自分も頑張らなくていいのでは」といった風潮が広がることがあります。
また、努力や成果が正当に評価されないと感じた優秀な人材が、他社へ転職してしまうケースも増加します。このような悪循環が続くと、離職率が上昇し、組織の活力や競争力が大きく損なわれます。
情報漏洩・内部不正リスク
窓際社員が不満を抱えたまま在籍し続けると、情報漏洩や不正行為につながるリスクもあります。組織から疎外感を感じている社員が、意図的に不正行為に及ぶケースも報告されており、IT環境ではUSBデバイスやクラウド経由のデータ持ち出しや不正利用が懸念されます。
企業としては、セキュリティリスクの可視化など、リスクの早期発見と対策が重要です。
■ 解雇の可否について
窓際社員の問題を解決するために「解雇」を検討する企業もありますが、日本の労働法制では簡単に解雇することはできません。特に、業務を与えていないだけでは「解雇の正当な理由」とは認められないケースが多く、慎重な対応が求められます。
そのため、企業は解雇以外の選択肢も含めて、適切な対応策を検討する必要があります。
窓際社員を「クビにできない」と言われる理由
労働契約法第16条では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。これを満たさない場合、解雇は 無効 と判断される可能性が高いです。
特に、窓際社員の場合、業務を与えていないこと自体が企業側の責任とみなされるため、「仕事をしていないから」という理由だけでは解雇は認められません。また、長年勤続している社員ほど、解雇が難しくなる傾向があります。このため、企業は窓際社員の解雇に慎重にならざるを得ません。
能力不足や消極性だけでは解雇できない:成果が出ていないだけでは合理的理由に該当しない
配置転換での対応が前提:まずは適材適所の再配置や教育研修で改善努力を行うことが求められる
不当解雇リスク:訴訟や労働審判になった場合、企業側が不利になることが多い
解雇が認められるケース・認められないケース
窓際社員の解雇が認められるかどうかは、個別の事情によって異なります。
たとえば、業務命令違反や重大な規律違反、著しい能力不足が明確な場合は、解雇が認められることもあります。
一方で、単に「仕事がない」「成果が出ていない」といった理由だけでは、解雇は認められません。企業は、解雇の前に配置転換や教育指導など、他の手段を講じることが求められます。
認められるケース:重大な服務規律違反、著しい能力不足が長期間改善されない場合
認められにくいケース:上司との相性が悪い、受け身な態度、業務が少ないから不要と判断する場合
解雇以外の選択肢を提示するのが現実的
現実的には、窓際社員に対して解雇以外の選択肢を提示することが適切です。
たとえば、配置転換や職務内容の見直し、再教育・研修の実施、早期退職制度の活用などが挙げられます。これらの方法を通じて、本人の適性や希望に合った新たな役割を見つけることが重要です。また、定期的な面談やキャリアカウンセリングを行い、本人の意欲や能力を引き出す取り組みも効果的です。
配置転換やジョブローテーション:適性のある業務に再アサイン
教育研修・スキルアップ支援:ITリテラシーや専門知識の習得支援
評価制度の見直し:定量的なデータ(勤務実態・業務成果)に基づいた評価
退職勧奨:本人の合意を前提とした選択肢の提示
■企業の窓際社員への対応策
窓際社員の問題を放置せず、組織全体の生産性やモラルを維持するためには、企業として具体的な対応策を講じることが不可欠です。主な対応策としては、早期発見と状況把握、適切な配置転換や再教育、キャリア支援、評価制度の見直しなどが挙げられます。
また、ITツールを活用した業務の可視化や、定期的な面談・フィードバックも有効です。これらの取り組みを通じて、窓際社員の再活用やモチベーション向上を図ることができます。
主な対応策一覧
対応策カテゴリ | 具体的な施策例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
配置転換・業務調整 | ・適性のある部署への異動 ・プロジェクトベースでの一時的アサイン | 新しい役割での能力発揮、再モチベーション化 |
教育・研修 | ・リスキリング(ITスキル、最新ツール習得) ・マネジメント研修や社内OJT | 能力不足の補強、キャリア再設計 |
評価制度の見直し | ・業務ログや成果データを活用した定量評価 ・短期目標の設定と達成度の可視化 | 公平な評価、納得感の向上 |
コミュニケーション | ・定期的な1on1面談 ・キャリアカウンセリング | 孤立防止、将来像の共有 |
退職支援 | ・セカンドキャリア相談 ・希望退職・退職勧奨 | 双方にとって納得感のある出口戦略 |
● 評価制度・目標設定の見直し
評価基準が曖昧なままでは、社員は努力しても正しく評価されないと感じ、モチベーション低下につながります。目標を数値化・明確化し、定期的に見直す仕組みを導入することで、公平で納得感のある評価が実現できます。
● コミュニケーション・面談の方法
定期的な1on1面談やキャリア相談を行うことで、社員の不満や課題を早期に把握できます。双方向のコミュニケーションを重視し、単なる評価の場ではなく、成長や改善に向けた対話の場とすることが効果的です。
● 業務プロセスの可視化と実働時間の測定
PCログや業務データを活用して、社員がどの業務にどれだけの時間を割いているかを可視化することが重要です。これにより、成果が見えにくい業務を評価に反映できるだけでなく、負荷の偏りを解消し、適切な配置転換や研修につなげることが可能になります。
対応ステップ
現状把握
勤怠と実働の乖離を確認
PCログ・業務データを収集し、実際の貢献度を可視化
面談・フィードバック
上司・人事が現状を率直に伝え、改善余地を話し合う
短期的な改善目標を設定
再活用プランの実施
配置転換や研修を組み合わせ、成果を評価
成功事例を社内に共有して組織全体の理解を促進
改善が見られない場合の選択肢
公平な評価データをもとに、処遇見直しやキャリア支援を行う
データに基づく客観的マネジメントの重要性
窓際社員(窓際族)への対応を感覚や主観だけで行うと、不公平な扱いや誤った判断につながりやすくなります。そのため、勤怠データや業務ログ、PC操作記録などの客観的データに基づいてマネジメントを行うことが重要です。業務実績や行動データを可視化し、適切な評価や配置を行うことで、窓際社員の早期発見や再活用が可能となります。
またITツールの活用により、窓際社員だけでなく、組織全体の生産性向上にもつながります。
■窓際社員へのマネジメントにも最適な『Eye“247” Work Smart Cloud』
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、社員の業務状況やパフォーマンスを可視化し、客観的なデータに基づいた人事評価や再活用策の判断をサポートするクラウドサービスです。このツールを導入することで、窓際社員の問題を早期に把握し、組織全体の生産性向上やモラル維持に役立てることができます。
また、データに基づく公平な評価が可能となり、社員一人ひとりの適性や強みを活かした配置転換やキャリア支援も実現しやすくなります。
窓際社員の早期発見に役立つログ管理
『Eye“247” Work Smart Cloud』は、PC操作ログやアプリの利用時間を収集し、実際の勤務状況を可視化します。これにより、業務量が極端に少ない社員、不正行為、業務怠慢の兆候を早期に発見することが可能です。
さらに「勤怠乖離チェック」機能を活用することで、勤怠記録と実際の稼働状況の差異を正確に把握できます。特にテレワークのように勤務実態が見えにくい環境においても、潜在的な窓際社員を早期に察知し、適切な対応につなげることができます。
▼勤怠乖離チェック

配置転換や再活用の判断材料としてのデータ活用
『Eye“247” Work Smart Cloud』で取得したPCログデータを分析することで、社員が成果を出せない理由が「本人の能力不足」なのか「配置のミスマッチ」なのかをより正確に判断しやすくなります。
たとえば、特定の業務で作業効率が著しく低い場合はスキル不足が疑われ、逆に能力はあるのに業務への適性が合っていないケースでは配置転換が有効といえます。
こうした分析結果は、人材の再配置やスキルアップ研修、リスキリング施策など具体的な改善策へと直結させることができ、組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。
客観的な数値で公平な人事評価を実現
データに基づいた評価は、主観的な偏見を排除し、公平性を高めます。社員にとっても納得感のある評価となり、モチベーション維持や業務への前向きな姿勢につながります。
『Eye“247” Work Smart Cloud』を活用することで、業務ログや成果データから客観的な評価が可能です。評価プロセスの透明性が向上することで、組織全体の信頼感が高まり、離職率の低下や人材定着にも寄与します。
また、経営層にとっても人材活用の方針を戦略的に立案しやすくなるといったメリットがあります。
■まとめ:企業として窓際社員の放置はNG
窓際社員(窓際族)は、本人のキャリア停滞だけでなく、企業全体の生産性や組織風土に深刻な悪影響 を及ぼします。無駄な人件費や生産性の低下、モラルの低下、情報漏洩リスクなど、放置することでさまざまなリスクが拡大します。日本の労働法制上、解雇は簡単ではありませんが、配置転換や再教育、ITツールの活用など、現実的な対応策を取ることが重要です。
特に『Eye“247” Work Smart Cloud』のようなツールを活用することで、早期発見・適切な対応・公平な評価が実現しやすくなります。
企業としては、窓際社員を放置せず、組織全体の活性化と持続的成長を目指しましょう。
この記事のポイント
|