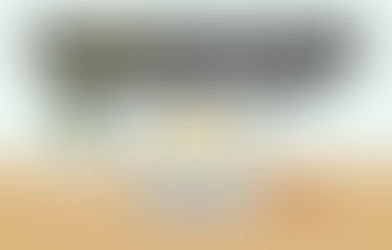なぜ「残業の常態化」はおかしいのか?会社と自分を守るチェックポイント
- FuvaBrain
- 9月29日
- 読了時間: 11分
更新日:2025年9月29日

長時間労働が当たり前になっている職場に違和感を覚えたことはありませんか? 「残業の常態化はおかしい」と感じる直感は正しく、放置すれば会社にも個人にも深刻なリスクをもたらします。
この記事では、「残業の常態化」という言葉の意味や問題点、なぜそれが会社や自分にとってリスクとなるのか、そして具体的な解決策やチェックポイントについてわかりやすく解説します。
目次
残業常態化を判断する基準(45時間・80時間・100時間)
「残業の常態化」は違法のリスクが高い
社会の意識変化と働き方改革
残業常態化の主な原因一覧
人手不足と業務量のバランス
企業文化と評価制度の影響
業務の見える化不足が招く負の連鎖
効果的な残業削減の制度と取り組み
「見える化」でムダな残業をなくす方法
健康を守るために残業常態化を防ぐ取り組み
業務時間を数値で把握する仕組み
部署ごとの偏りを客観的に確認する
データを活用した公平な評価と改善
『Eye“247” Work Smart Cloud』で「残業常態化」を解決する
勤怠とPCログの突合で乖離をチェック
部署・個人の業務量を可視化
■なぜ「残業の常態化」はおかしいのか
残業が常態化している職場は、単に仕事量が多いだけでなく、組織や働き方に根本的な問題を抱えている可能性があります。本来、残業は一時的な業務の繁忙やイレギュラーな対応のために発生するものであり、毎日・毎月のように続くのは異常な状態です。
このような状況が続くと、従業員の健康やモチベーションが損なわれるだけでなく、企業としても法的リスクや生産性低下、離職率の上昇といった深刻な問題に直面します。
残業の常態化を判断する基準(45時間・80時間・100時間)

残業の常態化を判断する際には、月間の残業時間が重要な目安になります。日本の労働基準法では、36協定に基づき月45時間を超える残業は原則禁止とされており、これを常態化すると違法リスクが高まります。さらに、月80時間を超えると「過労死ライン」に達し、深刻な健康被害の恐れがあります。加えて、月100時間に迫る働き方は労災認定の対象となる可能性が高くなり、企業に重大な責任をもたらします。
これらの基準を超える状態が続く場合は、職場環境や業務体制の抜本的な見直しが不可欠です。管理職は自分自身や部下の残業時間を定期的に確認し、基準を超えていないかを常にチェックしましょう。
「残業の常態化」は違法のリスクが高い
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間および1週40時間以内とされています。原則の労働時間を超える場合は、36協定の締結・届出が必須です。
ただし、36協定を結んでいても時間外労働の上限は月45時間・年360時間とされており、臨時的な特別な事情がない限り、これを超えることは違法になります。特に、月45時間を超える残業が年6か月を超えると「残業が常態化している」と見なされ、労働基準監督署からの指導や是正勧告を受ける可能性が高まり、最悪の場合は企業名の公表や罰則の対象となります。さらに、長時間労働が原因で健康被害や過労死が発生した場合、企業の社会的信用は大きく失墜し、損害賠償責任を問われるリスクも発生します。法令遵守の観点からも、残業の常態化は決して放置できない問題です。
また、臨時的な特別事情があり労使が合意した場合でも、月100時間未満・年720時間以内という絶対条件を守る必要があり、これを超えると違法となります。
項目 | 内容 |
|---|---|
週40時間 | 原則労働時間。1日8時間・週40時間を超えると36協定の終結が必須。 |
月45時間 | 36協定に基づく時間外労働の原則上限。年6か月を超えると是正勧告や罰則対象に。 |
年360時間 | 通常の36協定に基づく時間外労働の年間上限。これを超えると労働基準法違反となる。 |
年720時間 | 特別条項を適用した場合でも超えてはならない時間外労働の年間の絶対上限。 |
月100時間未満 | 特別条項があっても超えてはならない時間外労働の絶対上限。 |
社会の意識変化と働き方改革
近年、「長時間労働=美徳」という価値観は薄れています。働き方改革や健康経営の推進によって、企業には労働時間の適正管理やワークライフバランスの確保が一層強く求められています。
また、SNSや口コミサイトで「ブラック企業」として悪評が拡散するリスクも高まっています。優秀な人材を確保し、企業イメージを維持するためにも、残業常態化を放置することはできません。
今こそ、企業も個人も「残業は当たり前ではない」という意識を持ち、主体的に働き方を見直すことが必要です。
■残業の常態化が起こる原因を見極める
残業が常態化してしまう背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
単に業務量が多いだけでなく、人員配置や企業文化、評価制度、業務の見える化不足など、組織全体の仕組みやマネジメントの問題が根底にあることが多いです。
まずは自社や自分の職場で、どのような原因が残業の常態化を招いているのかを正しく把握することが、改善への第一歩となります。
残業常態化の主な原因一覧
残業が常態化する主な原因は多岐にわたります。以下に代表的な原因をまとめました。
主な原因 | 内容 | 影響例 |
人手不足・採用難 | 必要な人数を確保できず、一人あたりの残業時間が増加する | 残業に頼って業務を回す体制になる |
業務量・タスク配分の偏り | 業務が特定の人に集中する/属人化が進む | 特定社員だけが残業常態化 |
評価制度・企業文化 | 長く働くことを評価する文化が残業常態化を助長する | 残業が奨励される雰囲気に |
業務効率化・見える化不足 | 業務の進捗や負荷が見えにくく、問題が表面化せず改善が遅れる | 生産性低下による残業の増加が発生 |
人手不足と業務量のバランス
少子高齢化や採用難の影響で人材不足が深刻化し、一人あたりの業務負担が増加しています。人手不足の状態が続くと、限られた従業員に過度な業務が集中し、残業が常態化しやすくなります。さらに、業務量の不均衡や属人化が進むと、特定の部署や個人に負担が偏りがちになります。
こうした状況を放置すれば、従業員の疲弊や離職を招き、結果として人手不足と残業常態化の悪循環が深刻化します。そのため、最適な人員配置や外部リソースの活用による負担軽減が必要です。
企業文化と評価制度の影響
「残業している人が頑張っている」と評価される企業文化や、労働時間の長さで評価される制度が残業の常態化を助長します。このような風土では、効率的に仕事を終わらせるよりも、長く働くことが美徳とされがちです。結果として、不必要な残業やサービス残業が横行し、従業員のモチベーションや健康を損なう原因となります。
成果やプロセスに基づく制度設計へ移行し、管理職自らが残業削減を実践することが大切です。
業務の見える化不足が招く負の連鎖
業務の進捗や負荷が見えにくい職場では、どこに問題があるのか把握しづらく、残業が常態化しやすくなります。負の連鎖を断ち切るためには、業務の見える化を進め、PCログやタスク管理で誰がどの業務をどれだけ抱えているかを明確にすることが不可欠です。
見える化によって、業務の偏りや無駄を発見しやすくなり、適切な対策が打てるようになります。
■企業と従業員を守るためのチェックポイント
残業の常態化を防ぐためには、企業と従業員双方が意識して取り組むべきポイントがあります。これらを実践することで、健全な職場環境を実現しやすくなります。
効果的な残業削減の制度と取り組み
残業削減のためには、企業として明確な方針や制度を設けることが不可欠です。たとえば、ノー残業デーの導入やフレックスタイム制、在宅勤務の推進など、柔軟な働き方を実現する取り組みが効果的です。また、残業の事前申請制や、残業時間の上限設定、定期的な業務棚卸しなども有効です。
従業員一人ひとりが自分の働き方を見直すきっかけにもなります。
ノー残業デーの導入
フレックスタイム制・在宅勤務
残業の事前申請制
残業時間の上限設定
「見える化」でムダな残業をなくす方法
業務の見える化は、ムダな残業を減らすための有効な手段です。タスク管理ツールや勤怠管理システムを活用し、誰がどの業務をどれだけ抱えているかを可視化しましょう。
これにより、業務の偏りやボトルネックが明確になり、適切な人員配置や業務分担が可能になります。
また、進捗状況を定期的に共有することで、早期に問題を発見しやすくなります。
健康を守るために残業常態化を防ぐ取り組み
長時間労働は心身の健康に大きな悪影響を及ぼします。企業は従業員の健康を守るため、定期的な健康診断やストレスチェック、産業医による面談などを積極的に実施しましょう。また、従業員自身も適度な休息やリフレッシュ、セルフケアを心がけることが大切です。
健康を守る取り組みは、結果的に生産性向上や離職防止にもつながります。
定期健康診断・ストレスチェック
産業医面談の活用
適度な休息・リフレッシュの推奨
■ 残業の常態化を是正するために必要な「仕組み」と「ツール」
残業の常態化を根本から解決するためには、企業が積極的に「仕組み」と「ツール」を導入し、業務の効率化と適正な労働時間管理を実現することが不可欠です。
従来の紙や口頭での管理では限界があり、デジタルツールを活用することで、業務の進捗や残業状況をリアルタイムで把握できるようになります。また、データに基づいた客観的な評価や改善が可能となり、従業員の負担軽減やモチベーション向上にもつながります。
業務時間を数値で把握する仕組み
業務時間を正確に把握することは、残業削減の第一歩です。
勤怠管理システムやPCログ管理ツールを導入することで、従業員一人ひとりの労働時間や業務内容を数値で可視化できます。これにより、サービス残業や申告漏れを防ぎ、実態に即した労務管理が可能となります。また、データをもとに業務の偏りや無駄を分析し、効率化のための具体的なアクションを検討できます。
勤怠管理システムの導入
PCログ管理ツールの活用
業務時間の自動集計
部署ごとの偏りを客観的に確認する
残業の常態化は、部署やチームごとに偏りが生じやすい傾向があります。部署ごとの労働時間や業務量を可視化することで、どこに負担が集中しているのかを客観的に把握できます。
この情報をもとに、業務の再配分や人員配置の見直し、サポート体制の強化など、具体的な改善策を講じることが重要です。
公平な職場環境づくりのためにも、部署ごとの状況を定期的にチェックしましょう。
データを活用した公平な評価と改善
データに基づく評価制度を導入することで、労働時間や成果を客観的に評価できるようになります。これにより、長時間働くことが評価されるのではなく、効率的に成果を上げる従業員が正当に評価される環境が整います。
また、データを活用して業務プロセスの改善点を洗い出し、継続的な業務改善サイクルを回すことが可能です。公平な評価と改善が、残業の常態化を防ぐ大きな力となります。
労働時間・成果のデータ化
客観的な評価基準の設定
業務プロセスの継続的改善
■『Eye“247” Work Smart Cloud』で「残業の常態化」を解決する
残業の常態化を解決するための最新ツールとして注目されているのが『Eye“247” Work Smart Cloud』です。このクラウドサービスは、勤怠データとPCログを連携させることで、実際の労働時間と申告内容の乖離を自動でチェックできます。また、ダッシュボードによる社員一人ひとりの業務量の可視化など、残業リスクの早期発見と対策を強力にサポートします。
企業規模や業種を問わず導入しやすく、働き方改革の推進にも最適なツールです。
勤怠とPCログの突合で乖離をチェック
『Eye“247” Work Smart Cloud』では、勤怠データとPC操作ログを突合し、打刻時間と実際の労働時間の乖離を確認できます。これにより、残業常態化の原因となるサービス残業を発見し、労務管理の適正化につなげることができます。
また、他社勤怠システムの勤怠データをCSVで取り込むことが可能で、1日のPC操作の開始・終了時間と、勤怠打刻による出勤・退勤時間を並べて表示できます。
▼勤怠乖離チェック 実際の画像

部署・個人の業務量を可視化
『Eye“247” Work Smart Cloud』では、部署単位や従業員ごとの業務量を可視化できます。
これにより、部門や従業員一人ひとりの業務量の偏りや労働時間、集中度の違いを把握し、課題を明確化したうえで効果的な改善策を講じることが可能です。
▼部署・ユーザー別集計 実際の画像

■まとめ:「残業の常態化はおかしい」と気づいた時点から変えていく
残業の常態化は、企業にも従業員にも大きなリスクとデメリットをもたらします。「残業が当たり前」と感じた時点で、その状況を見直し、原因を特定し、具体的な対策を講じることが重要です。
法律や社会の変化に対応し、最新のツールや仕組みを活用することで、健全な職場環境と高い生産性を実現できます。
『Eye“247” Work Smart Cloud』は残業常態化を解決する有効な選択肢です。
まずは小さな一歩から、残業の常態化をなくすための行動を始めましょう。
この記事のポイント
|